ChatGPTなどのAIツールが現れて以来、AIで文章を生成する方法が注目されています。
実際、就職活動においても、志望動機をAIで作成する方が増加中です。
しかし、「AIで志望動機を作成したとバレたら、選考に不利になるのではないか?」と不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、志望動機の作成でAIを利用する際のリスクや注意点に加え、AIに頼りすぎず自分の言葉で熱意を伝えるための工夫について解説します。併せて、プロのアドバイザーに相談できる就職支援サービスについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
AIを上手に賢く活用しながら、あなたの強みと意欲がしっかりと伝わる志望動機を作り上げ、就職活動を成功させましょう!
志望動機をAIで書いたら本当にバレる?
近頃、ChatGPTなどのAIを活用して志望動機を作成するケースが増えています。
「簡単に文章が生成できて、時間短縮になる」「自分では思いつかない表現が出てくる」といったメリットがある一方で、「AIで書いたことがバレたら、選考に落ちるのでは?」という不安の声も根強く存在します。
はたして、AIで作成した志望動機は、本当に「AIが書いた」と見抜かれてしまうのでしょうか?
バレる可能性は高い!
結論から言えば、AIで作成した志望動機は、バレる可能性が十分にあります。
なぜなら、企業の採用担当者は何百、何千という志望動機に目を通しているため、定型的な表現や表面的な内容、企業への理解が不足している文章はすぐに見抜けるからです。
AIにすべてを任せて安易に作成した志望動機は、どこか「薄っぺらい」と感じられやすく、AIを使ったことが見抜かれて評価が下がるだけでなく、その時点で不採用となる可能性が高いでしょう。
AIが書いた志望動機が見抜かれるケース
では、具体的にどのような志望動機が「AIが書いた」と判断されてしまうのでしょうか。
以下に、AIを使用したと判断されやすい典型的なケースを4つ解説します。
抽象的で具体性がない
AI(人工知能)は、「機械学習」と「ディープラーニング(深層学習)」という技術を使い、大量のデータを自動的に学習します。
そして、複雑で多様なデータのなかから見つけ出したパターンやルールを、予測結果や分析結果として出力します。
しかし、AIは具体的な指示がなければ、個々の経験や感情などのニュアンスを深く理解することはできません。
そのため、AIに作成を丸投げした志望動機は、表面的な言葉が並び、「貴社の○○に魅力を感じました」「社会に貢献したいと考えています」といった抽象的な表現に終始しがちになります。
これでは、具体的なエピソードや経験に基づいた説明がないため、読み手の心に響かず、本当にその企業で働きたいという熱意が伝わりません。
志望動機でお悩みなら「書類選考なし」という選択肢も!
「就職カレッジ」なら……
- 書類選考なしで人柄重視の優良企業と面接
- 35歳以下なら経歴・スキルに自信がなくてもOK
- 内定後のフォローもあって定着率92%以上
オリジナリティに欠けた内容
AIを利用して志望動機を作成すると、どうしても表現や構成が似通ってしまうことが多くなります。
ほかの応募者と類似した内容は、採用担当者に「使い回しではないか」「自分で深く考えていないのではないか」という印象を与えてしまうでしょう。
オリジナリティに欠けた、「この人ならではの理由」のない志望動機は、不採用理由の一つになってしまいます。
企業の理念や事業内容にずれや誤りがある
AIはインターネット上の情報をもとに文章を生成しますが、必ずしもその情報が最新かつ正確であるとは限りません。
加えてAIの特性から、企業特有の雰囲気や文化といった細やかな点について正確に理解することは難しいと考えられます。
したがって、AIが作成した志望動機には、企業の理念や事業内容に対する誤解、認識のずれが生じる懸念が大きいといえるでしょう。
企業研究をしていないことがバレる
誤った内容が書かれた志望動機を読んだ採用担当者は、「本当にうちの会社について調べたのかな?」と疑念を抱くかもしれません。
AIが作成した志望動機をノーチェックで提出するのは非常にリスクが高く、自分で企業研究をしていないことがすぐに見抜かれてしまうでしょう。
文章の表現や言い回しが不自然
AIが作成した文章は一見自然に見えても、よく読むと「言い回しが堅すぎる」「日本語として少し違和感がある」と感じることがあります。
英語を直訳したような表現や、過剰に丁寧な言い回しは、人間が書いた自然な文章とは異なり、不自然さが目立ちやすいポイントです。
「話し言葉」と「書き言葉」が混ざりやすい
AIで志望動機を作成する際に特に注意したいのは、「話し言葉」と「書き言葉」が混ざっていないかという点です。
例えば敬語では、「相手の会社」のことを話すときは「御社(おんしゃ)」と言いますが、文章に書くときは「貴社(きしゃ)」と表現するのが一般的です。
日本語には複雑なルールがあり、AIが正しく使いこなせない場面も多く、入念なチェックが必要でしょう。
参考:文化庁 敬語の指針(平成19年2月2日文化審議会答申)
企業が求める人物像とのミスマッチ
AIは、与えられた指示にしたがって文章を構成します。
そのため、適切な指示を与えられていないと、企業が求めている人物像とかけ離れた志望動機ができあがってしまうことがあります。
ミスマッチを起こしたままの内容では、「この人は、うちに合わないかも」と企業が判断してしまうおそれがあります。
自分の価値観や経験が企業のニーズと合致しているか、という確認は欠かせません。
採用担当者が志望動機で重視しているポイント
それでは、企業の採用担当者は志望動機のどこに注目し、何を知りたいと思っているのでしょうか。
AIに頼る前に、採用担当者が重視するポイントを、自分でしっかりと理解しておきましょう。
熱意や経験が志望動機に結びついているか
採用担当者は、応募者がその企業に対してどれほどの熱意を持っているのかを知りたがっています。
単に「興味がある」というだけでなく、「なぜこの企業で働きたいのか」「自分の経験が企業でどのように役立つのか」といった具体的な理由や根拠を求めているのです。
過去の経験と志望動機がしっかりと結びついていれば、入社後の活躍を想像しやすくなり、熱意もより深く伝わるでしょう。
企業についての理解度とマッチング
また、採用担当者は、応募者が企業についてどれくらい理解をしているのかも重視しています。
採用後、長期にわたり働いてもらいたいと考えるのは、企業として当然のことです。
そのため、職種への適性だけでなく、「社風に合うのか」「愛社精神を持って働いてくれそうか」という観点からも応募者との相性を見ています。
こうした評価のポイントを押さえるためにも、企業の理念やビジョン、具体的な事業内容、職場の雰囲気、業界内での立ち位置などを丁寧に調べておくことが不可欠です。
そのうえで、自分の経験や価値観が、企業の目指す方向性と一致していると明確に伝えられれば、採用担当者も「この人ならきっと活躍してくれるはずだ」と前向きに受け止めてくれるでしょう。
バレるリスクを回避!上手なAI活用方法
ここからは、「AIっぽさ」を感じさせずにAIで自分らしい志望動機を作成するために、意識しておきたい4つのポイントをご紹介します。
自己分析と企業研究を丁寧に行なう
AIを上手に使うには、まず「自分を知る」「企業を知る」という土台づくりが大切です。
自分の強み、過去の成功体験や失敗から学んだこと、仕事に対する価値観、将来のキャリアプランなどを確認しましょう。
自分の強み、経験、価値観を深く掘り下げる
過去のアルバイト経験などを振り返り、自分がどのような役割を果たし、どのような成果を上げたのかを具体的に洗い出します。
まずは、自分が担当してきた業務を細かく書き出してみましょう。
併せて、仕事をするなかで、褒められたことや失敗したことも書き出してみます。
これらの作業を通して、仕事の経験から何を学んだのか、どのようなときにやりがいを感じたのか、自分が大切にしている価値観は何かといったことを見つめなおすことができ、自分の強みを把握する手がかりになるでしょう。
自分の経験から強みを見つける方法は、以下の記事にも詳しく書かれています。こちらもぜひ参考にしてください。

企業理念、事業内容、求める人物像を理解する
企業の理念や事業内容、求める人物像を理解するために、いわゆる「企業研究」にもしっかり取り組みましょう。
やり方としては、企業のWebサイト、ニュース、インタビュー記事などを読み、企業の方針や取り組みを一つひとつ確認していきます。
ポイントになりそうなことは、すべて書き留めておくとよいでしょう。AIに指示を出す際に役立ちます。
企業が求める人物像については、求人の採用情報欄に記載されているケースがほとんどです。
さらに、実際に活躍している社員がどのような人物かを知り、現場で働く社員のコメントを参考にすると、大いに役に立つでしょう。
そして、企業研究で得た情報をもとに、自分の強みや経験がその企業でどのように活かせるのかを具体的に考えます。
AIを志望動機のヒントやアイデアの参考として使う
AIはすべてを任せられる万能ツールではなく、あくまで「補助ツール」であることを忘れてはいけません。
厚生労働省でも、“AIは、人間の労働の一部を代替するのみならず、高度な道具として人間を補助することにより、人間の能力や創造性を拡大することができる” という指針を示しています。
引用:厚生労働省 人間中心のAI社会原則(平成31年3月29日 統合イノベーション戦略推進会議決定)
AIで志望動機を作る際に最終的な目標としたいのは、「人が書いたような魅力ある内容の文章」を作成することです。
そのため、AIと対話しながら、新たな視点を得るためのヒントやアイデアを出してもらうのが、適切な使用方法といえるでしょう。
AIで表現のバリエーションを広げよう
例えば、「熱意」という言葉を、別の表現に言い換えるとします。
AIに「熱意をほかの表現に置き換えてください」と指示を出すと、「情熱」「意欲」「強い思い」など、意味の近い言葉をいくつか提案してくれます。
これらのなかから、自分の気持ちに最も合うものを選べば、より自分らしいニュアンスを伝えることができ、表現にも深みが出てくるでしょう。
AIが書いた志望動機を「自分の言葉」でさらに改善する
AIが作成した志望動機は、どこか無難でありきたりに感じてしまうことは少なくありません。そのようなときは、自分の言葉を加えて改善してみましょう。
AIが作成した文章をベースとして活用しつつ、自分の実体験や価値観を織り交ぜてカスタマイズすることで、よりオリジナルで心に響く志望動機へと仕上がります。
具体的なエピソードや経験を盛り込む
まずAIに、過去の具体的なエピソードを盛り込む指示を出します。
「〇〇のアルバイトで、△△という問題に直面したが、□□という工夫をすることで、無事に問題を解決できた」といった具体的な経験は、あなたのオリジナリティを出す強力な武器になります。
志望動機にオリジナリティを加えることで説得力が増し、採用担当者にあなたの能力や人となりをより深く理解してもらえるようになるでしょう。
自分の意欲を伝える
「なぜその企業で働きたいのか」「企業のどのような点に魅力を感じているのか」という熱意や意欲も、ぜひ入れておきたいところです。
AIに指示を出すときは、企業の理念や事業内容に対する共感だけでなく、「自分の目標と企業の成長目標との関連性」や「自分が企業にどう貢献できるか」といった視点も加えてみましょう。
入社意欲の高さを伝えられるだけでなく、別の応募者との差別化にもつながります。
企業にマッチする人材であることをアピールしよう!
志望動機を自分で考えるにしてもAIを使うにしても、「自分が企業にマッチする人材である」とアピールすることが、採用に近づくための最大のポイントです。
単なる自己アピールではなく、「この会社だからこそ自分が活かせる」という視点を意識すると、より魅力的な内容になるでしょう。
なお、AIで志望動機を作成する際に、適切な指示を出す方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。
指示出しの例も記載していますので、こちらもぜひ参考にしてください。
▶関連記事

志望動機が不安なときは「人」にも相談してみよう
もし、AIを活用しても志望動機に不安が残るときは、「人」に相談することも検討してみましょう。
無料の就職支援サービスを利用してみる
相談できる「人」を見つけたいときは、就職支援サービスの利用がおすすめです。
ハローワークや民間の就職支援サービスでは、キャリアアドバイザーによる個別相談や、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策など、無料でさまざまなサポートを受けられます。
応募する求人について具体的な相談ができるのは、人が行なっているサービスならではといえるでしょう。
「人」が話を聞いてくれる安心感
AIとは違い、対面やオンラインで直接話を聞いてくれる「人」の存在は、就職活動において大きな安心材料です。
就職支援サービスのキャリアアドバイザーは、あなたの状況や希望を丁寧にヒアリングし、客観的な視点から具体的なアドバイスをしてくれます。
実際にアドバイザーの助言によって、志望動機の内容がより具体的になったり、自分では気付かなかった強みに気付けたりすることもあります。
誰かに話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になるでしょう。
AIよりも心強いサポートが受けられる
プロのキャリアアドバイザーならではの強みは、企業の採用傾向に熟知していることです。
そのため、あなたの強みや適性を効果的にアピールする方法だけでなく、企業の具体的な採用情報や選考のポイントなどを教えてくれる場合もあります。
人に相談することで、AIでは得られないような貴重な情報に触れられたり、就職活動のヒントを得られたりするかもしれません。
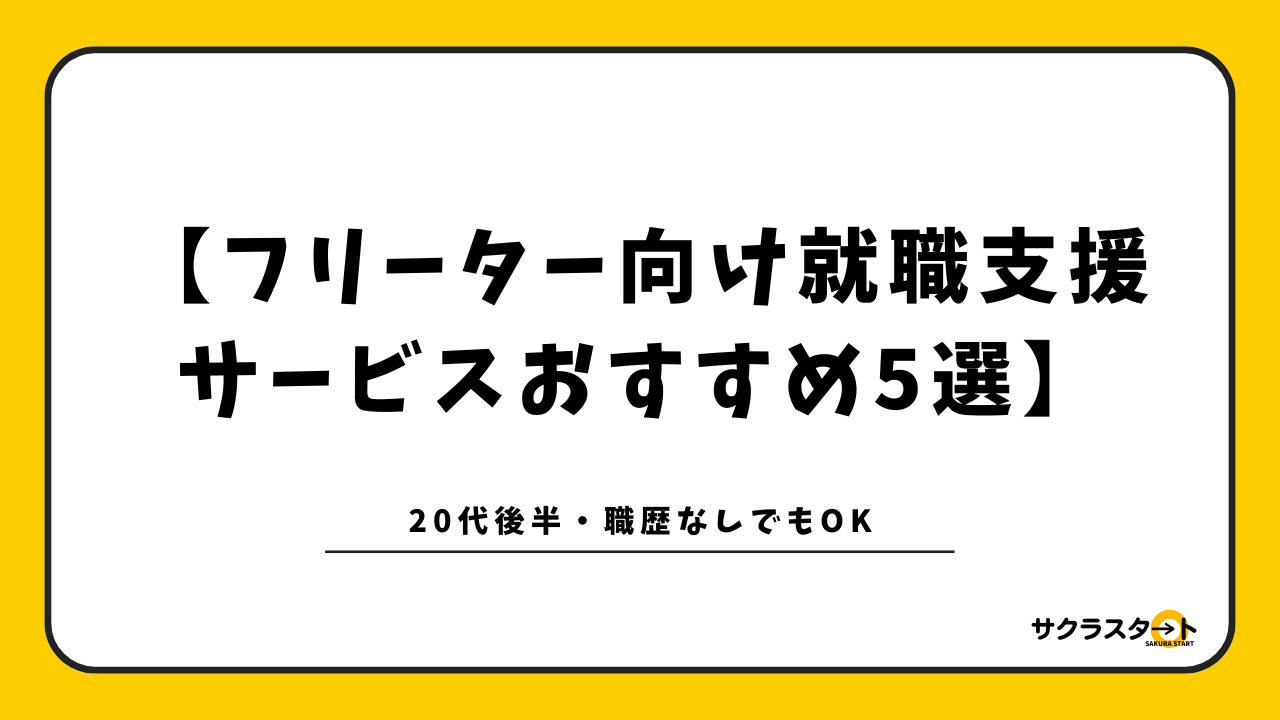
自分らしい言葉でAIを賢く活用!
AIは志望動機づくりの強力な味方ですが、使い方を間違えると、誰にでも当てはまる無難で魅力のない文章しか生成してくれません。
重要なのは、AIの力を借りつつ、自分の言葉や想いをしっかりと込めることです。
ツールを「賢く使う」意識が、あなたらしさを引き出す鍵になるでしょう。
AIはあくまでツール。あなた自身の想いを乗せることが大切
AIは、あくまであなたの可能性を引き出し、表現するためのサポート役にすぎません。
大切なのは、あなた自身の想いや経験をどう言葉にして届けるかということです。
自分の言葉でしっかりと肉付けできれば、唯一無二の魅力的な志望動機が完成するでしょう。
AIだけでは不安…そんなときは人を頼ってみる
AIを活用しても不安が残る場合は、遠慮なく就職支援サービスなどの「人」を頼ってみてください。
プロの視点からのアドバイスは、あなたの自信につながり、きっと就職活動を成功に導いてくれるはずです。
AIも人の助けも、自分の強みを引き出すための手段です。
上手に活用して、あなたらしい志望動機を作成し、就職活動の成功へとつなげましょう。

