「この求人、もしかしてブラック企業……?」
あなたは求人票を前にして、そのような疑念にとらわれていませんか?
この記事では、求人票に潜む「ブラック企業の危険なサイン」と、安心して正社員の職に就くための方法を徹底解説していきます。
求人票の言葉や数字の裏に隠された企業の本音と「ブラック企業の見分け方」を知り、後悔のない就職を目指しましょう!
ブラック企業を見分ける自信がなく、応募をためらってしまう
あなたは「ブラック企業だったらどうしよう」という強い不安を抱えながら、求人票を眺めているのではないでしょうか。
「正社員になりたいけど、もしブラック企業に入ってしまったら……」と考えると、なかなか応募に踏み切れない。その気持ちよくわかります。
「ブラック企業だけは避けたい」と考えるのは当然のこと
「絶対にブラック企業だけは避けたい」と思うのは、当然の感情です。
あなたはきっと、真面目に働きたいと考えているはず。
しかし、入社後に不当な長時間労働やハラスメント、低賃金に直面したら、心身ともに疲弊し、せっかくの「正社員として頑張って働いていく」という前向きな気持ちまで失ってしまうかもしれません。
「危険な会社を見抜きたい」と願うのは、正当な自己防衛本能といえるでしょう。
ブラック企業を見分けるには?
では、どうすればブラック企業を見分けられるのでしょうか?
実は、多くのブラック企業は求人票に「危険なサイン」を出しています。
ブラック企業を見分ける知識とあなたの警戒心を組み合わせることで、自信を持って企業を選択できるようになるでしょう。
そもそも「ブラック企業」とは何なのか?
「ブラック企業」とは、そもそもどのような企業を指すのでしょうか。
まずはその実態を知っておきましょう。
法令違反に抵触しそうな労働環境が常態化している会社の俗称
ブラック企業は、法律上の明確な定義はありません。
一般的には、従業員を酷使し、法令違反に抵触しそうな労働環境が常態化している会社の俗称として使われています。
具体的には、以下のようにコンプライアンスを無視する企業が該当します。
- 長時間労働やサービス残業が常態化している
- 休みが少なく有給休暇が取りづらい
- ハラスメントやいじめが放置されている
- 達成困難なノルマが設定されている
- 退職を認めない、不当に退職へと追い込む
労働環境の悪さから、離職率が高いことが特徴
ブラック企業は劣悪な労働環境のため、従業員が長く定着しません。
結果として、常に求人を出しているにもかかわらず、人の入れ替わりが激しく、離職率が非常に高いという特徴があります。
なぜブラック企業は求人票で「良い顔」をするのか?
ブラック企業が実態を明かしたら、誰も入社してくれないでしょう。
ブラック企業は常に人手不足に悩んでいるため、求人票では実態とかけ離れた魅力的な言葉を並べ、「働きやすい会社」であるかのように見せかけます。
だからこそ、その裏にある本当の姿を見抜くことが重要なのです。
ブラック企業が出す危険なサイン!求人票チェックポイント【ありがちなワード編】
ここからは、ブラック企業が求人票で使いがちな「危険ワード」に焦点を当てて解説していきます。
「魅力的に見えるけれど危険な言葉」がどのようなものか、注目してください。
「アットホーム」「和気あいあい」「風通しが良い」が危険信号な理由
多くの求人票で見かける「アットホームで和気あいあいとした職場です」「風通しが良い会社です」という言葉。
これを聞くと、「人間関係が良好で、居心地が良さそう」と感じるかもしれません。
しかし、この言葉は以下のような意味を持つ危険なサインの可能性があります。
- 会社の制度や規則が曖昧
- 既存の人間関係に新入社員が馴染みにくい
- 残業や飲み会が強制され、プライベートを侵害する
- 上司や先輩社員の押しつけや圧力
本当に働きやすい職場であれば、制度や職場環境の詳細が求人票に明記されているはずです。
「未経験者大歓迎」の裏に潜む本音とは?
「未経験者大歓迎」という言葉は、職歴に自信がないあなたにとって、とても魅力的に映るかもしれません。
なかには、本当に教育体制が整っていて、未経験からでも活躍できる企業もあるでしょう。
注意したいのは「誰でもいいからとにかく人が欲しい」というケースです。
ブラック企業で「未経験者大歓迎」と書かれている場合は、教育が不十分なまま、いきなり責任のある仕事を任されたり、周囲のサポートがないまま成果を求められたりする可能性があります。
このワードを見た際は、教育体制や研修制度、入社後のフォロー体制が整っているかを念入りに確認しましょう。
曖昧な「事業内容」「職務内容」はブラックの兆候
「事業内容」と「職務内容」が曖昧な企業は、ブラック企業の可能性が高いといえます。
何をしている会社かわからない、流行り廃りの激しい事業に複数手を出しているといった企業のなかには、違法性の高い事業を行なっているケースもあるため注意が必要です。
また、職務内容が不明瞭だと「何でも屋扱いされる」「求人票にない仕事をさせられる」などのリスクがあります。
入社後に「こんなはずじゃなかった……」と後悔しないためにも、事業内容や職務内容が詳しく記載されているか、しっかり確認しましょう。
常に「急募」「積極採用中」の状態
求人サイトで、常に「急募」や「積極採用中」の企業は、慢性的な人手不足で離職率が高い可能性があります。
ずっと募集をかけている背景には「労働環境が悪く、社員が定着しない」といった理由が隠れているかもしれません。
もし気になる企業が頻繁に人を募集している場合は、疑問を持ち、募集理由を確認するようにしましょう。
数字は嘘をつかない!求人票チェックポイント【注意したい数字編】
言葉はいくらでも飾れますが、数字は嘘をつきません。
求人票に記載されている「数字」にも着目してみましょう。
給与欄の罠!「固定残業代(みなし残業)」のカラクリを知っておこう!
給与欄で注意したいのが、「固定残業代(みなし残業)」です。
これは、会社が規程した一定時間分の時間外労働や休日・深夜労働の割増賃金が毎月定額で支払われるものです。
なお、固定残業代は、規程された時間分の残業をしたかどうかにかかわらず支払われます。
固定残業代には、何時間分が含まれているかチェック!
固定残業代は、求人票に「基本給○万円、固定残業代(○時間分)○円を含む」といった形で記載されています。
重要なのは、「何時間分の残業代が含まれているか」という点です。
例えば、「固定残業代45時間分」と書かれていれば、毎月45時間までは残業しても残業代が別途支給されないことになります。
仮に毎日1時間程度残業したとすると、月間の残業時間はざっくり20時間から30時間となるでしょう。
もし、固定残業時間がこれらを大幅に超える時間数(45時間など)で設定されている場合、それは長時間労働が前提となっている可能性があります。
なお、法定労働時間は「1日8時間、週40時間」と定められています。
参考:厚生労働省
労働時間・休日
固定残業代 を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。
基本給が低く固定残業代が高い企業は要注意
基本給を低く抑え、固定残業代を含めて一般的な給与水準にしている企業は要注意です。
例えば「基本給が15万円、固定残業代が10万円」と記載された求人票があったとしましょう。
その場合、基本給と固定残業代を合わせてやっと月25万円の給与になります。
また、賞与の算出基準は基本給とする企業が多く、基本給が低いと実質的に年収が下がります。
さらに、固定残業代の金額が高いということは、その分の長時間残業がある、とも読み取れるでしょう。
残業代が固定残業代に含まれないケースもある?
固定残業代で規程された時間を超える残業が発生すると、企業はその超過分の残業代を別途支払う義務があります。
しかし、ブラック企業のなかには、「固定残業代があるから、どれだけ残業しても残業代は出ない」と社員に誤った説明をしたり、実際に支払わなかったりするケースがあります。
求人票に「固定残業代」の記載がある場合は、それが何時間分で、その時間を超えた場合の残業代はきちんと支払われるのか、面接時などに確認することをおすすめします。
年間休日数……それ、本当に休める?
年間休日数は、ワークライフバランスを測る重要な指標です。
この数字にも、ブラック企業を見分けるポイントが隠されています。
「週休2日制」と「完全週休2日制」は天と地の差!
求人票の休日欄でよく見かける「完全週休2日制」と「週休2日制」ですが、実はこの2つには大きな違いがあります。
- 完全週休2日制
-
毎週、確実に2日休める制度です。
例えば、シフト制で休日が変則的であっても、必ず週に2日の休みを取得します。
- 週休2日制
-
月1回でも2日休みの週があればOKという制度です。
つまり、毎週必ず2日休みがあるわけではなく、1週だけ2日休みがあり、ほかの週は1日休みしかないケースも想定されます。
以上のとおり、「週休2日制」と書かれている場合は、年間休日数が少なくなる傾向があります。
安定した休日を望むなら、「完全週休2日制」の企業を選びましょう。
年間休日「105日」は危険水準?
日本の労働基準法では、週に1日、または4週に4日の休日を設けることが義務付けられています。
これに加え、祝日や年末年始休暇、夏季休暇などを含めたものが「年間休日」です。
例えば、完全週休2日制を導入している企業であれば、年間120日程度が年間休日の基準となります。
これには、週2日の休みと祝日が含まれます。
では、なぜ「年間休日105日」が危険水準なのでしょうか?
それは、労働基準法で決められた労働時間と休日から計算すると、年間休日の最低ラインが105日となるからです。
休みが少ないと、まとまったプライベートな時間が取れず、心身ともにリフレッシュできないまま働き続けることになります。
疲労やストレスが溜まり、体調不良にもつながりかねません。
なお、厚生労働省が2024年12月に発表した2023年の年間休日の平均は「116.4日」でした。
年間休日の目安としては、できれば120日以上、少なくとも110日以上と考えておくとよいでしょう。
出典:厚生労働省
労働時間・休日
令和6年就労条件総合調査の概況
「福利厚生」思っているのと違うかも?求人票のチェックポイント【気を付けたい制度・規程編】
福利厚生とは、従業員の働きやすさやモチベーション向上を目的として、企業が給与以外に提供する報酬やサービスのことです。
この福利厚生にも、注意すべき点があります。
「交通費支給」は全額支給?大事なのは規程!
交通費に関しては、労働基準法による規程はなく、企業独自の規程となります。
求人票に「交通費支給」とだけ書かれている場合は、全額支給なのか、上限があるのか、支給規程について確認が必要です。
例えば、「交通費:上限1万円まで支給」と書かれている場合、実際の交通費が1万円を超えても、会社は1万円までしか支給してくれません。
自宅から会社までの交通費が毎月2万円かかる場合、毎月1万円は自己負担になってしまいます。
また、車通勤の交通費支給は、企業によって規程が大きく異なります。
ガソリン代の算定方法はもちろん、会社の敷地内に駐車場がない場合は、別途駐車場を借りる必要があり、その費用が全額自己負担となるケースも多いでしょう。
有給休暇の取得実績を書いていない企業に注意!
有給休暇の取得は、労働者に与えられた当然の権利です。
しかし、有給休暇があっても、実際に取得できるかは別問題です。
ブラック企業では、「人手不足で休めない」「上司から嫌味を言われ取得しにくい」など、事実上取得困難なケースが多々見られます。
従業員に年5日の有給休暇を取得させる義務がある
有給休暇が年10日以上付与される従業員に対して、会社は年5日取得させる義務があることをご存知でしょうか。
これは、労働基準法において2019年4月から施行されています。
つまり、有給休暇を取得させない会社は違法なのです。
優良企業であれば、有給休暇の取得を奨励し、求人票にも取得実績日数や消化率の社内平均を記載しているでしょう。
もし、有給休暇について「あり」としか書かれていない場合、その企業では有給休暇がどれくらい取得されているのか、面接時などに質問してみることをおすすめします。
参考:厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 2019年4月施行
あえて「詳細を書かない」ブラック企業の意図とは
ここまで見てきたように、ブラック企業は、あえて詳細な情報を求人票に記載しない傾向があります。
これは、求人の内容を曖昧にすることで、求職者に「良い想像」だけを与え、入社につなごうとする手口です。
求人票に不明瞭な点が多いと感じたら、それは警戒すべきサインだととらえましょう。
ベンチャー企業とブラック企業を混同しないように注意
ブラック企業だとすぐ判断すべきではない企業として挙げられるのが「ベンチャー企業」です。
ベンチャー企業とは、新しい技術やアイデアで急成長を狙う新興企業のことです。
ベンチャー企業は設立から日が浅く、少人数で業務を回していたり、福利厚生が十分に整っていなかったりする場合もあるでしょう。
しかし、これは必ずしも「ブラック企業」を意味するものではありません。
ベンチャー企業は社員とともに成長し、各種制度を整えていく
ベンチャー企業の多くは、社員の声を反映しながら環境を整える姿勢が見られます。
ブラック企業は社員を使い潰すのに対し、ベンチャー企業は社員とともに成長しようとしている点が大きく異なります。
ベンチャー企業に応募する際は、経営者のビジョンや、社員の成長に対する投資意識など、表面的な情報だけでなく、その企業の将来性や理念も確認してください。
【参考】ホワイト・優良企業の求人票にはどのようなことが書いてある?
ホワイト企業や優良企業は、求人票でどのような情報を開示しているのでしょうか。
ブラック企業との違いを知ることで、より良い企業を見抜く力を養いましょう。
包み隠さず詳しい情報を公開している
ホワイト企業や優良企業の求人票は、以下のように、「包み隠さず、できるだけ詳細な情報を公開している」という特徴があります。
- 職務内容や業務の流れを詳しく記載
- 給与や手当の内訳を明示
- 年間休日数とその内訳を記載
- 福利厚生の制度や取得実績を記載
- 研修内容や教育体制を具体的に説明
- 月平均残業時間を記載
- 定着率や平均勤続年数を公開
- 社員インタビューや写真で職場の雰囲気を伝える
このように、ホワイト企業は、求職者が安心して応募できるように、可能な限りの情報を透明性高く公開しています。
これは、自社の労働環境に自信がある証拠であり、「入社後のミスマッチをなくしたい」という誠実な姿勢の表れでもあるでしょう。
求人票だけではわからない「見えない部分」に潜むリスク
ここまで、求人票におけるブラック企業の見分け方を解説してきました。
しかし正直なところ、求人票の情報だけではすべてを見抜くことはできません。
求人票の「見えない部分」にも、ブラック企業のリスクが潜んでいることがあります。
実際に働いてみないとわからない部分は大きい
求人票にいくら良いことが書かれていても、以下のように実際に働いてみないとわからない部分は大きいでしょう。
重要度も高く、あなたの働きやすさに影響します。
- 社員同士の人間関係
- 上司のマネジメントスタイル
どんなに注意しても「一人で全部見抜く」のは難しい
この記事を読み進めたあなたは、「求人票からブラック企業を見分ける方法」という知識を手に入れました。
しかし、それでも「ブラック企業を完全に見抜く」のは至難の業です。
ブラック企業は巧妙に情報を隠そうとします。
また、企業の公式Webサイト以外で展開されているインターネット上の企業情報や口コミサイトは、偏った情報や古い情報も含まれます。
「以前のブラックな労働環境が今は改善された」という企業も多くありますが、すべてを鵜呑みにするのは問題があるでしょう。
疑念があるときは「応募しない」勇気を持つ
あなたが求人票を見て引っかかる部分があったり、疑念が拭えなかったりする場合は、無理に応募しないという勇気を持つことも大切です。
焦って応募し、ブラック企業に入社したら、あなたの貴重な時間とエネルギーを無駄に消耗する結果となってしまいます。
不安を感じたら、別の選択肢を探しましょう。
プロの力を借りて「まともな会社」を見つけるのも一つの手
「自分一人では、やっぱり不安」「もっと確実な方法で、まともな会社を見つけたい」そう思ったなら、ぜひプロの力を借りることも検討してみてください。
フリーターなど未経験者の就職支援に特化したサービスでは、あなたの経歴や希望を丁寧にヒアリングしたうえで、適性のある求人を紹介してくれます。
さらに、求人票だけではわからない企業の内部事情を教えてくれることもあるでしょう。
就職支援サービスの利用は、より良い会社へスムーズに就職したいあなたに最適な手段です。
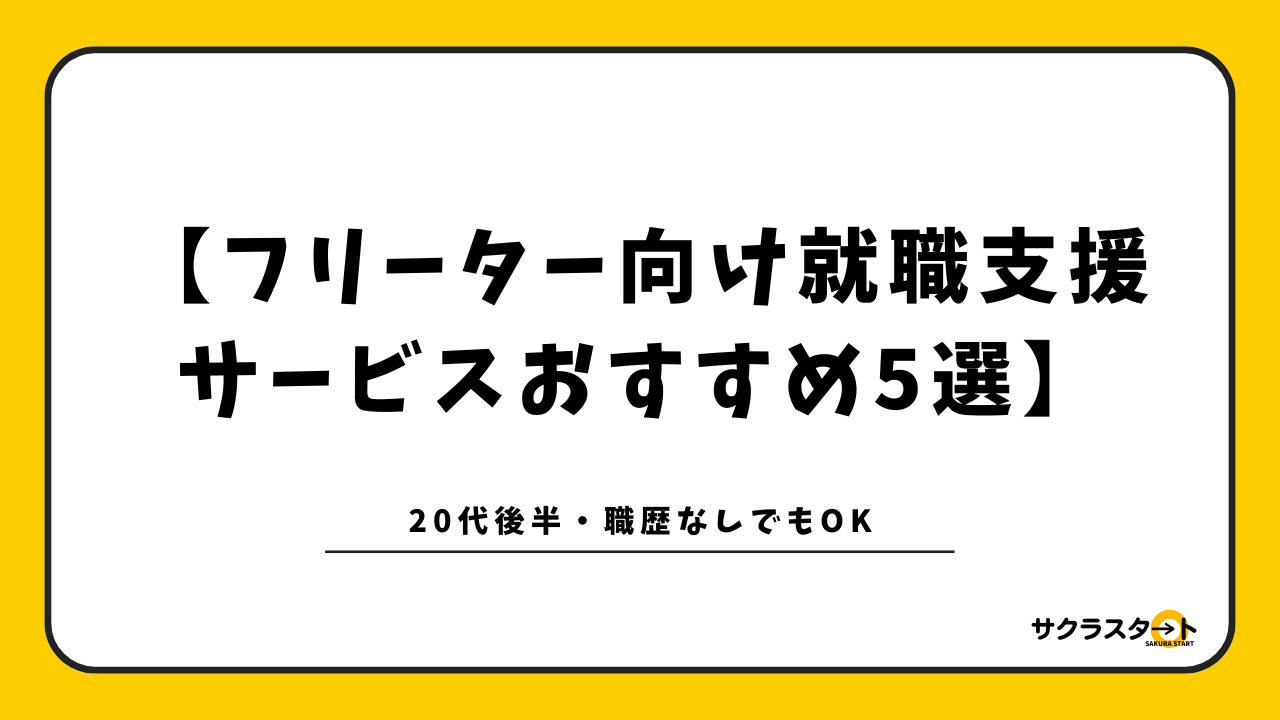
求人票を見抜く「目」を養い、後悔のない就職をしよう!
この記事では、求人票から危険なサインを発見し、ブラック企業を見分ける具体的な方法を解説してきました。
この方法を実践すれば、きっと後悔のない就職が実現できるでしょう。
そして、一人の就職活動が不安なときは、ぜひ信頼できる支援を活用し、あなたにぴったりな会社を見つけてください!

