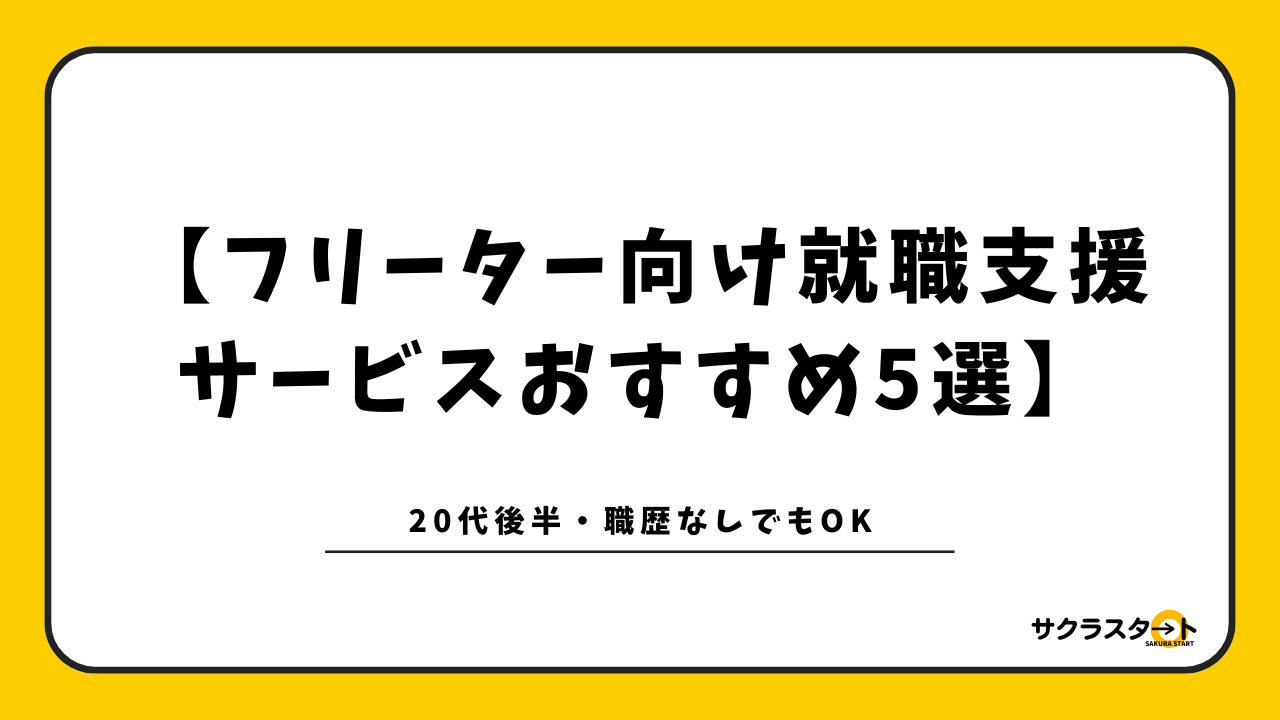就活のために求人票を見ていると「この情報は本当なの?」「なんとなく信用できない」のように感じることもあるのではないでしょうか。
今後の人生が変わるかもしれない場面で、「だまされたくない」「失敗したくない」と考えるのは自然なことです。
しかし、あまり疑心暗鬼になると、どの求人も嘘や都合の良いことばかりに見えてきて応募できなくなってしまうかもしれません。
そこで本記事では、求人票の嘘や誤解を避ける方法を紹介します。職場や仕事とのミスマッチを防ぎ、後悔のない就活とするために、ぜひ役立ててください。
なぜ求人票は「嘘」ばかりになる?
これまでのアルバイト経験から、「求人は慎重に選びたい」という気持ちが強い人もいるでしょう。
入社してから後悔しないためには、自分に合う求人を選ぶことが大切です。
とはいえ、求人票にはわかりにくい部分が多く、「実態と異なるのでは?」と感じることもよくあります。
それには、以下のような理由があることを知っておきましょう。
自社を良く見せて応募者を集めたいから
厚生労働省は、求人票で次のような表示を禁止しています。
- 虚偽の表示
- 誤解を生じさせる表示
つまり、企業は求人票に、応募者をだますようなことを書いてはいけません。
一方、企業としては自社の求人を目立たせて、必要な人材を集めたいと考えるのが一般的です。
そのため、過度な誇張などはできないものの、求人票の内容を少しでもよく見せようとさまざまな工夫をしています。
これは、求人票に書かれていることが嘘だと思われやすい理由の一つでしょう。
たとえ企業側には悪意がなくても、自社を良く見せようとした結果、応募者からは嘘に見えてしまうことが少なくないのです。
誤解されやすい用語があるから
求人票には、独特の言い回しが使われることも少なくありません。これが、嘘だと思われやすいもう一つの理由でしょう。
例えば、「未経験者歓迎」と書かれていたとき、意味を勘違いしてしまうことが考えられます。
「経験のないジャンルだけれど、歓迎してくれるなら」と思い切って応募しても、実際には経験者のほうが優先的に採用されるケースがあるのです。
用語の意味はこのあと説明しますが、この場合、企業は嘘をついているわけではありません。
応募者から嘘のように見えてしまうのは、用語の本来の意味と解釈のズレによって誤解が生じているためです。
求人票はここをチェック!「嘘」のない求人の見分け方6選
求人票の嘘や誤解を避けて本来の意味を見抜くには、具体例を知っておくと役に立つでしょう。ここでは、実際の求人票にありがちな例を挙げながら、正しい意味を説明します。
- 【応募資格】「未経験者歓迎」や「必須スキル」の意味を理解しよう
- 【業務内容】「誰にでも簡単な仕事」は実際の作業を確認しよう
- 【給与】「モデル年収」には残業代などの手当も含まれると考えよう
- 【休日・休暇】「週休2日制」「年間休日◯日」は有給休暇の実態と併せて確認しよう
- 【福利厚生】「法定外福利」の内容と使いやすさをチェックしよう
- 【社風・雰囲気】「アットホーム」「風通しが良い」などの表現は参考程度にとらえよう
それぞれ、詳しくみていきましょう。
【応募資格】「未経験者歓迎」や「必須スキル」の意味を理解しよう
求人票の「未経験者歓迎」は、「未経験者を優遇する」ではなく「未経験でも応募はできる」という意味です。
言葉から受ける印象と事実が「まったく逆」のように思えて、驚く人も少なくないでしょう。
企業がこのような表現を用いる背景には、実際にどれくらいの応募が集まるかわからないため、求人を出す段階では応募条件を広めにしておきたいという考えがあります。
結果として経験者から十分な数の応募があれば、あえて未経験者を採用する必要はありません。
つまり、実際に優遇されているのは経験者のほうです。
また、「必須スキル」が曖昧で、自分が当てはまるのかわからないケースもよくあります。例えば、「◯◯の経験◯年以上」「基本的なパソコンスキル」などと書かれている場合です。
このような曖昧な表現は、「こういう人に活躍してほしい」というイメージを表しているのだと解釈すればよいでしょう。
厳密な条件がわからなくても、入社後のミスマッチはなさそうだと思えれば特に問題はありません。
【業務内容】「誰にでも簡単な仕事」は実際の作業を確認しよう
求人票では、「誰にでもできる簡単な仕事です」のような表現もよく使われます。
これは、一般的には「スキルがなくても入社後にやり方を覚えられるので大丈夫」などの意味です。
どのような仕事をするのかがわかっているなら、応募の際の安心材料となるでしょう。
ただし、仕事の内容が具体的に説明されていない場合は要注意です。
実際には覚えることが非常に多く、体力的にもハードな仕事を美化しているのかもしれません。
求人票の情報だけで「自分にもできそうだ」と安易に考えるのではなく、勤務地や作業内容などを具体的に確認して、納得したうえで応募することが大切です。
【給与】「モデル年収」には残業代などの手当も含まれると考えよう
求人票には、「モデル年収(年収例)」が記載されていることがあります。
これらは、実際に受け取れる給与よりも高い金額になっていると考えるのが無難でしょう。
モデル年収は通常、手取りの額ではなく、税金などが引かれる前の総支給額を表すものです。
また、多くの場合は平均的な残業代や住宅手当なども含まれています。
就職してから受け取れる実際の給与額については、基本給と各種手当の内訳を確認しておくことが重要です。
なお、なかには「固定残業代(みなし残業)」を採用している企業もあるかもしれません。その場合は、毎月の残業が一定時間を超えない限り、固定の残業代を受け取れます。
固定残業代は本来なら労働者にメリットのある制度ですが、求人票のうえでは十分な確認が必要でしょう。
毎月の残業代を固定で受け取れる分、基本給が少ない金額に設定されていることも考えられるためです。
【休日・休暇】「週休2日制」「年間休日◯日」は有給休暇の実態と併せて確認しよう
求人票でよく見る「完全週休2日制」と「週休2日制」は、意味が異なります。
前者は毎週2日の休みがありますが、後者は月に1回以上・週2日の休みがあるという意味です。これだけでも、毎月の休日日数に差があります。
上記と併せて、年間の休日日数も確認しておきましょう。
カレンダーどおりに毎週土日と祝日が休みだとすると、年間の休日はおおむね120日となります。
しかし、求人票に「年間休日120日」と記載されていても、カレンダーどおりに休めるとは限りません。
これは、有給休暇をすべて消化した場合の日数を載せている企業もあるためです。
有給休暇の取得率が低い企業では、実際の休日はもっと少なくなると考えられます。
【福利厚生】「法定外福利」の内容と使いやすさをチェックしよう
福利厚生は、会社員として安心して働くために大切な制度です。健康保険や厚生年金などは「法定福利」といって、どの企業も法律にしたがって提供しています。
求人票では、企業が独自に提供する「法定外福利」をチェックしましょう。
具体的には、住宅手当・通勤手当・社員食堂・育児休暇・レジャー施設の割引などが挙げられます。
もし自分の価値観と合うものが見つかれば、それはあなたにとって「良い制度」だといえるでしょう。
ただし、福利厚生は実際に利用できなければ無駄になってしまいます。
制度として使いやすいかどうか、従業員にどれくらい利用されているかなどを確認しておくと安心です。
【社風・雰囲気】「アットホーム」「風通しが良い」などの表現は参考程度にとらえよう
「アットホームで風通しが良い職場です」のような表現も、求人票ではよく使われます。こうした抽象的な表現は、ほかの内容を補足するものだと考えましょう。
求人票で業務内容や待遇についてしっかりと説明されているのなら、本当にアットホームな職場の可能性があります。
例えば、小さな事務所で従業員同士の結束が固く、仕事以外でも有意義な交流ができるといったことが想像できるでしょう。
もしかすると、今後の人生にもプラスになるような、良い経験が待っているかもしれません。
ただし、それ以外にアピールポイントのない求人には注意が必要です。
この場合は、「本当にアピールできる部分がない」「何か言えないことがある」といった事情が考えられます。
繰り返しになりますが、実際に応募する前に、どのような仕事なのかを具体的に確認することが大切です。
目利きに自信がないなら”プロのサポート“も検討してみては?
「就職カレッジ」なら……
- 書類選考なしで人柄重視の優良企業と面接
- 35歳以下なら経歴・スキルに自信がなくてもOK
- 内定後のフォローもあって定着率92%以上
求人票の「嘘」で後悔しないために!応募する前の心構え
入社してから「思っていた職場や仕事内容ではなかった」などと後悔しないためには、求人票に記載されている情報の意味を自分で判断することが大切です。応募する前に、以下のような心構えがあるとよいでしょう。
それぞれ詳しく紹介します。
求人票の情報は鵜呑みにしない
ここまで説明してきたように、求人票は嘘が書かれているように見えることがよくあります。
誤解が生じやすい用語や、曖昧な表現が使われるケースが少なくないためです。
求人票の情報を鵜呑みにして応募すると、入社してから「こんなはずではなかった」と思うことになるかもしれません。
悪意がある場合は別として、こうした嘘や誤解が生じるのは、企業側に「自社をよく見せたい」という意図があるためです。
この点をふまえて、「なぜこの書き方になったのか」のように、常に疑問をもって求人票の内容を確認することを心がけましょう。
違和感や疑問点は納得できるまで確認する
求人票の内容に疑問を感じたときは、そのまま放置しないことが大切です。
本記事では、実際の求人票にありがちな嘘の例を紹介しました。それらを参考にしながら、自分で納得できるまで本当の意味を確認しましょう。
ただし、求人票そのものから得られる情報は限られています。
何が本当のことなのかは、目の前の求人票だけをじっくり読んでもわからないかもしれません。その場合は、ほかの場所からも情報を得る必要があります。
企業の情報は多角的に調べる
求人票の真偽を確かめるために、その企業の情報をできる限り違う方向から集めて、付き合わせてみましょう。
これにより足りない情報が補われ、入社後のイメージもわきやすくなります。
このとき重要なのは、わからないことを徹底的に調べる姿勢です。
また、このあと説明するような、情報を多角的に収集するテクニックがあれば役立つでしょう。
求人票の「嘘」を見抜くための情報収集テクニック
ここでは、企業の情報を多角的に収集するためのテクニックを紹介します。
これらの方法で集めた情報を突き合わせることが、求人票の嘘を避けつつ、本来の意味を見抜くのに役立つでしょう。
複数の求人サイトを比較する
企業は必要な人材を得るために、仕事内容や職場の違いなどによって分けた数種類の求人を出すことがあります。
また、複数の求人サイトを利用して人材を募集するケースもみられます。
まずは、その企業が出している求人を検索して、内容を比較してみましょう。
どの求人サイトを見てもまったく同じ内容の求人票が載っているだけという場合もありますが、記載内容に違いがあるようなら、そこからわかることもあるかもしれません。
企業の公式サイトをよく読む
応募する企業の公式サイトをよく読むのは、情報収集の基本です。これから長く働くかもしれない職場のことなので、隅々までしっかりと確認しましょう。
公式サイトには、経営理念や沿革、事業内容やサービス紹介などが載っているのが一般的です。
「代表メッセージ」や「社員インタビュー」などのページがあれば、社風もある程度わかります。
また、「採用情報」のページで、求められる人材などについて説明している企業もあります。
仕事の内容や福利厚生の充実度なども、具体的にわかるかもしれません。
口コミサイトで企業の評判をチェックする
企業の口コミを集めたサイトも、有用な情報源の一つでしょう。
口コミは、その企業で働いたことがある人によるリアルな意見です。
個々の口コミの信ぴょう性については冷静に判断する必要がありますが、職場の雰囲気や、就職後の満足度などを具体的にイメージしやすくなります。
最終的に応募するかどうかを決める際にも、大いに参考になるでしょう。
SNSで企業名を検索する
SNSで公式アカウントを運営している企業は少なくありません。公式アカウントがある場合は、どのような情報が発信されているかチェックしておきましょう。
企業によっては、就職・転職の体験談や、職場の様子などが紹介されていることもあります。
また、企業名でSNS上の投稿を検索し、口コミの情報源とすることも可能です。
ただし、非公式の投稿は信ぴょう性が高いとはいえないので、あまり鵜呑みにせず参考程度にとどめましょう。
どのような企業なのか就活のプロに聞く
求人票の真偽を確かめるには企業についての情報収集が重要だといっても、自力でできることには限界があります。
すべて自分で調べるのは難しいと感じたら、「就職支援サービス」を活用するのも一つの方法です。
就職支援サービスでは、「就職アドバイザー」や「就職コンサルタント」などのプロに、就活のさまざまな相談ができます。
企業の情報についても、多数の求人を扱ってきたプロの視点で適切なアドバイスをもらえるでしょう。
また、非公開の求人や、より自分に合う企業の詳細な情報を提供してくれることもあります。
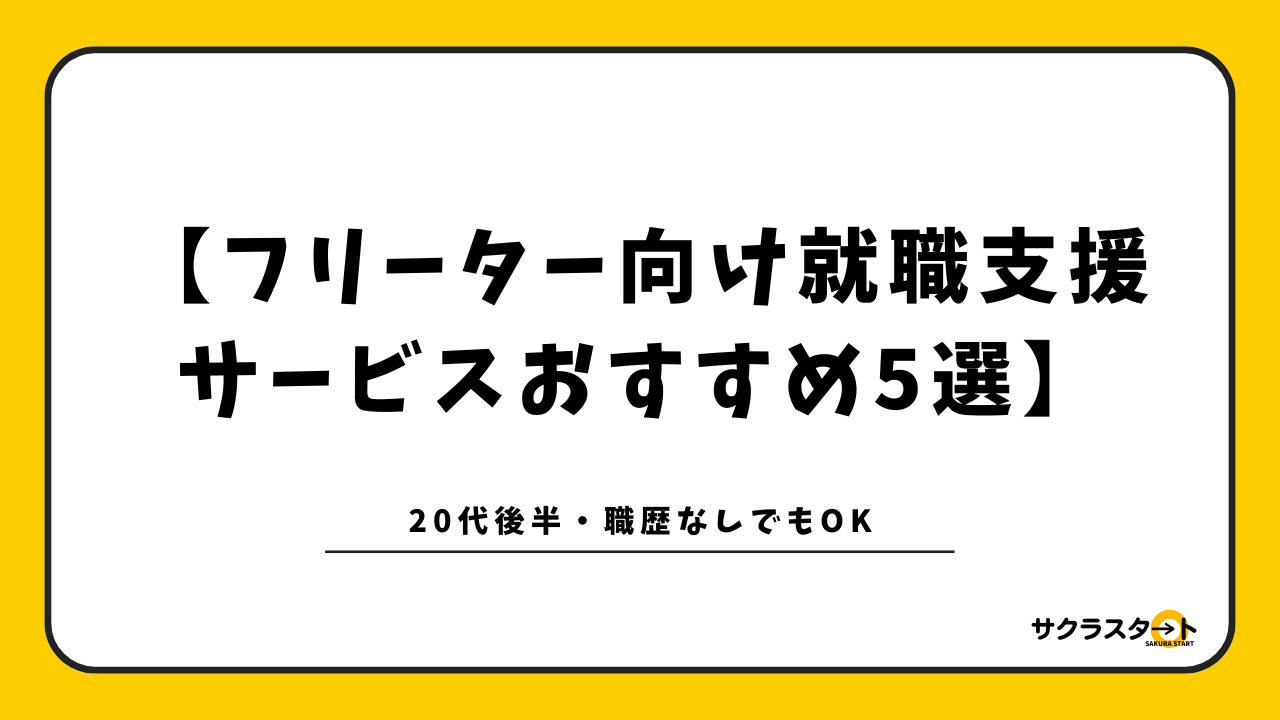
求人票の疑問点を面接で確認したいときの質問方法
求人票に嘘や誤解がないかなど、わからないことがあれば応募前に確認しておくのが理想です。
そのためには、就職支援サービスの活用も検討するとよいでしょう。
とはいえ、どうしても面接で確認したい疑問点も出てくるかもしれません。例えば、以下のようなことです。
面接でこうした質問をするときは、選考で不利にならず、失礼のない聞き方を心がけましょう。そのための質問方法について、例をあげながら説明します。
仕事内容について詳しく知りたい
仕事内容に関することは、面接でも比較的聞きやすいでしょう。積極的に質問すれば、仕事へのやる気を示すことにもつながるかもしれません。
次のように、実際の仕事を具体的にイメージした聞き方をすれば、印象も良くなります。
◯◯部の業務について、1日の流れはどのようになるか教えていただけますか?
給与や評価制度について教えてほしい
給与や評価制度など、「お金」にかかわることはデリケートな話題とみなされやすいため注意が必要です。
質問のしかたによっては、「お金や待遇にしか興味がない」という印象を与えてしまうかもしれません。
どうしても質問したい場合は、できる限り直接的な言い回しを避けましょう。
次のように、前向きで間接的な聞き方をするのがおすすめです。
どのようなスキルや資格があると、御社で活躍しやすいでしょうか?
どれくらい残業や休日出勤があるのか確認したい
「残業の少なさ」や「休日の多さ」を期待するような質問をすると、やる気を疑われてしまうかもしれません。
「働きたくない人なのでは?」と思われないように、仕事への意欲が伝わるソフトな尋ね方を心がけましょう。
みなさんは普段どれくらい残ってお仕事をされることが多いですか?
求人票との食い違いについて説明してほしい
面接で詳しい話を聞いてはじめて、求人票との矛盾点に気付くこともあるかもしれません。
その場合でも、矛盾を責めるような言い方をせず、丁寧な姿勢で質問しましょう。
求人票に記載されている◯◯について、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか?
まとめ:求人票はしっかり確認して後悔のない就活を
就活では、求人票の内容を信用できず、なかなか応募に踏み切れないこともあるでしょう。
入社してから「思っていた職場や仕事内容と違う」などと後悔しないためにも、求人票に書かれている本当の意味を、しっかりと理解する必要があります。
求人票は鵜呑みにしない!自分でも情報収集することが重要
求人票の内容は、たとえ企業側に悪意がなくても、嘘のように見えることが少なくありません。
就活で後悔しないためには、その理由を理解するとともに、独特の用語や曖昧な表現から本来の意味を見極める必要があります。
それには、求人票の記載内容を鵜呑みにせず、企業の情報を徹底的に収集する姿勢が大切です。
本記事で紹介した「嘘のない求人の見分け方」や「情報収集テクニック」を、ぜひ役立ててください。
限界を感じたら就活のプロに相談しよう
求人票の真偽は、ある程度までなら自分でも確かめられるでしょう。しかし、一人でできることには限界があります。
自分だけでは難しいと感じたら、就職支援サービスの活用も検討しましょう。
希望する企業の詳しい情報や、自分との相性などについて、就活のプロによる客観的なアドバイスを受けられます。
また、非公開の求人を紹介してもらえる可能性もあるので、もっと自分に合う企業が見つかるかもしれません。
就職支援サービスについては下記の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。