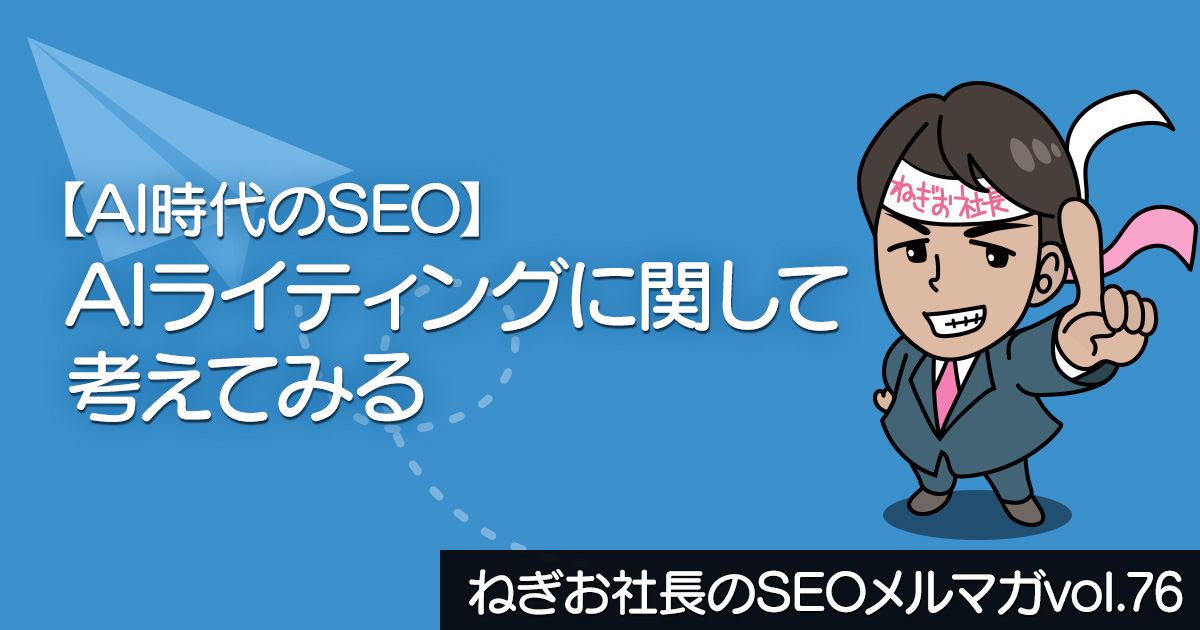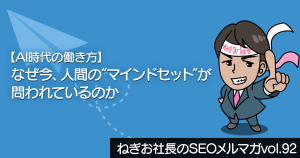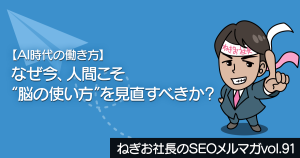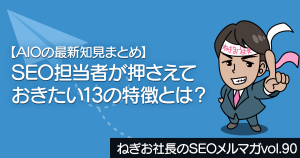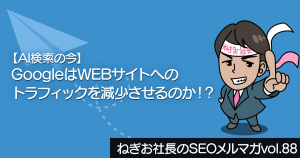ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この記事は、「ねぎお社長のSEOメルマガ」をメール配信したものを記事にしております。
ねぎお社長のSEOメールマガジン無料購読はこちら
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
こんにちは。サクラサクマーケティング株式会社、社長のねぎおです。
近年、AIライティング(AIによる文章生成)がSEOの世界でも大きな話題になっています。
特に、ChatGPTやGoogle Bard、Bing AIなどの登場により、コンテンツ制作のあり方が変化しつつあります。
社内でもAIの是非について、日々議論を交わしているのですが、現在のAIライティングブームに関して、SEO歴20年のねぎおなりの見解をまとめてみたいと思います。
もちろん、未来予測は難しいですが、1つの考えとしてご覧いただけますと幸いです。
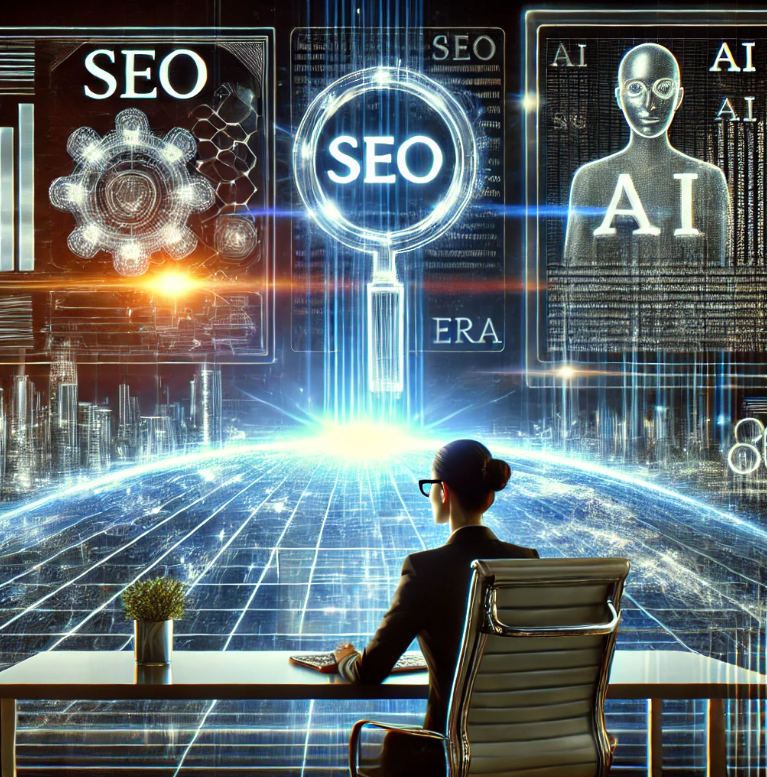
AIライティングの現状
近年のディープラーニングの飛躍的な発展により、AIは文章の意味をある程度理解し、一貫性のあるテキストを生成できるようになりました。
特にOpenAIのChatGPTや、GoogleのBard、MicrosoftのBing AIなどの登場によって、一気にAIライティングが身近な存在となりました。
これらのツールは以下のような用途で活用されています。
- 記事の下書き作成:ブログ記事やニュース記事の草稿を作成し、人間が校正・編集
- コピーライティング:商品説明文や広告文のアイデア出しをサポート
- コンテンツのリライト:既存文章の言い回しを変更・要約
現在、多くの企業やマーケターが試験的にAIライティングを導入し始めており、効率化やコンテンツ量産の手段として注目されています。
ただ、一方でその品質やSEOへの影響については賛否両論があります。
ここからは、ねぎおの私見を交えつつ、AIライティングがもたらす課題を考えてみましょう。
ねぎお社長の視点(AIに書かせるべきではない理由)
ねぎお自身の結論を先に言えば、現状では重要なコンテンツをAIに書かせるべきではないと考えています。
その理由をSEOの観点からいくつか挙げてみます。
(1) GoogleはAIコンテンツを判別できるのか?
まず気になるのは、「GoogleはAIが書いた文章を見抜けるのか?」という点です。
結論から言うと、完全に判別するのは難しいが、露骨なAI任せのコンテンツは検知され得るというのが業界の共通認識です。
- 完全に見分けるのは難しいが、露骨なAI任せのコンテンツは検知され得る
- Googleのジョン・ミューラー氏も、スパム対策チームが対応可能と発言
- 「AIか人間か」ではなく、コンテンツの品質が評価の鍵
(2) AIコンテンツの問題点
AIに文章を書かせる最大の問題点は、オリジナル性や独自性の欠如にあります。
- オリジナル性や独自性の欠如
- AIは膨大な既存データを学習して文章を作るため、新規性に欠ける
- 複数の人間が同じAIツールを使えば、似た内容の記事が大量に生まれる
- Googleは重複コンテンツを低評価(インデックスすらしない)する傾向にある
(3) 過去のコンテンツSEOブームとの比較
AIによる記事量産の流れを見ていると、2013~2016年頃に流行したコンテンツSEO大量生産時代を思い出します。
- 2013~2016年:クラウドソーシングによる記事量産ブーム
- キーワードを詰め込んだ低品質記事が氾濫
- 一時的に上位表示できたが、WELQ問題を契機に淘汰
- AIコンテンツも同じ轍を踏む可能性が高い
- 「とりあえずAIで記事を増やせばいい」は危険
(4) AIコンテンツは低品質とみなされる可能性
以上を踏まえると、たとえAIでそれなりに見栄えのいい文章を書けたとしても、総合的な品質評価では人間のオリジナルコンテンツに劣る可能性が高いと考えます。
- GoogleのHelpful Content Updateにより、価値の低い記事はランキングが下がる
- AI生成の内容が事実誤認や著作権侵害を含むリスクあり
- 「AIコンテンツはペナルティを受けるか?」 → 現時点では明確な制裁はないが、今後の動向次第
未知数な部分と今後の展望
AIライティングについて否定的な面を述べてきましたが、技術の進歩は日進月歩です。
未知数な部分も多く、未来予測に関しても考えてみたいと思います。
(1) AIライティングはどこまで進化するのか?
現在のAIはあくまで過去データの学習に基づいて文章を生成しています。
真に独創的なアイデアを生み出したり、最新の出来事にリアルタイムで対応したりする点では人間に軍配が上がります。
しかし、この先数年でAIの性能がさらに向上すれば、より高度な創造性や文脈理解を示す可能性もあります。
- 現在は過去データを学習して文章を生成
- 未来では、事実チェック機能や創造性の向上が期待される
(2) 人間のライターと共存できるのか?
AIと人間のライターは競合というより協働の関係になっていくと考えます。
すでに実践している方も多いですが、AIはリサーチや下書き作成、アイデア出しのアシスタントとして活用し、人間が最終的な肉付けや編集、独自視点の付与を行う使い方が有効です。
いわばAIはライターの「助手」や「ツール」として共存するイメージです。
- AI = 助手、ライター = 編集者の関係に
- リサーチや下書きをAI、仕上げを人間が行うハイブリッド運用が有効
(3) 企業がAIを活用する際のリスクと可能性
企業がコンテンツ制作にAIを導入する際には、リスクと可能性の両方を理解する必要があります。リスクとしては、前述のように品質低下によるSEO評価の悪化があります。
また、AIの出力した内容に誤情報が含まれるケースや、意図せず第三者の著作物に酷似した文章が生成されるケースも考えられます。
自社のブランドイメージを損ねたり、法的な問題(著作権侵害など)に発展したりする恐れもあるため、人間によるチェック体制は不可欠です。
- リスク
低品質コンテンツによるSEO評価の悪化
AIが生成した誤情報・著作権侵害のリスク
- 可能性
生産性の向上(ブレスト・下書き作成のスピードアップ)
商品データの説明文作成などの業務効率化
- 重要ポイント
AI任せにしない!
AIの強み(スピード)と人間の強み(創造力)を組み合わせる
結論:今後のSEO戦略
AIライティングの台頭によってコンテンツ制作の在り方は変わりつつありますが、SEOにおける基本原則は変わりません。
最終的に評価されるのは「誰が書いたか」ではなく「何が書かれているか」、すなわちコンテンツそのものの価値です。
今後のSEO戦略として特に重要だと考えるポイントをまとめます。
- オリジナル性・ユニーク性の高いコンテンツを作る
- 企業の経験談や専門家の見解を交えた独自コンテンツが重要
- ブランディングの強化
- AIでは築けない「企業の信頼性」を軸にSEO対策を進める
- 専門性・権威性(E-E-A-T)の追求
- 業界の専門家を巻き込んだコンテンツ作りが差別化の鍵
最後に改めて、Googleの下記、記事を一読てみましょう!
https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content?hl=ja
AIと共存する時代だからこそ、「人間にしか書けないもの」を意識することが重要です。
便利なツールは活用しつつ、読者に価値を届けるSEO戦略を練っていきましょう!
では、また!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■SEOコンサルティングのご相談は下記より、お気軽にご連絡をお待ちしております。
https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/seo-consulting#sec9
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー