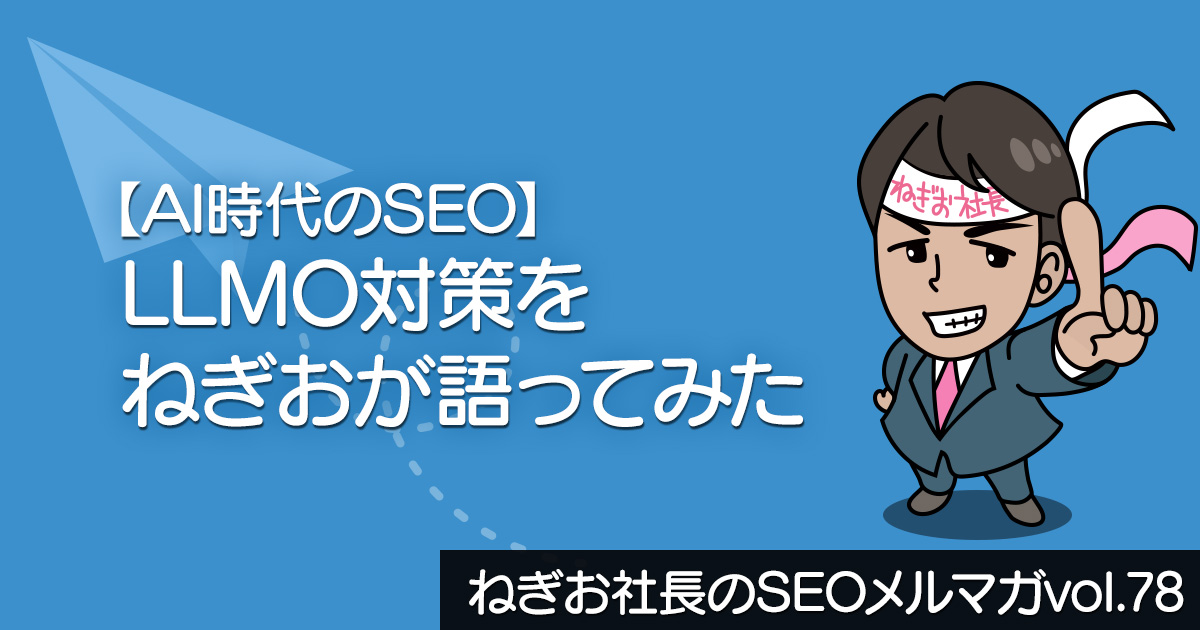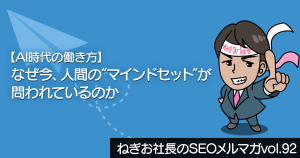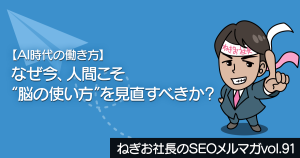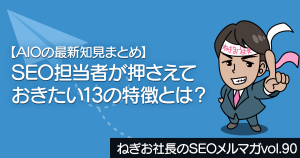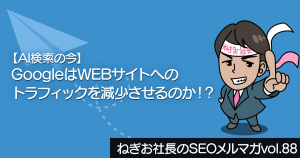ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この記事は、「ねぎお社長のSEOメルマガ」をメール配信したものを記事にしております。
ねぎお社長のSEOメールマガジン無料購読はこちら
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
こんにちは。サクラサクマーケティング株式会社、社長のねぎおです。
いつもメルマガをご愛読いただきありがとうございます。
最近はChatGPTをはじめとする生成AI(Generative AI)の活用が話題となり、私たちウェブサイト運営者にとって新たな挑戦と機会が生まれています。
今回は、そのようなAI時代におけるウェブ最適化「LLMO対策」について、ねぎおの考えをお伝えしたいと思います。

生成AIの利用増加とその影響
- ChatGPTをはじめとする生成AIの利用者数は、ここ1年で大幅に増加
- 情報収集手段として「AIに聞く」が一般化
- AIが引用・参照するサイトが、新たな流入チャネルになる可能性大
ここ数年で、ユーザーが情報を得る方法に大きな変化が起きています。
Google検索やSNSに加え、ChatGPT のような対話型の生成AIを使って質問し、回答を得るケースが急増しています。
いわゆる「AI検索時代」の到来です。
従来の検索エンジンを使う人は依然多いものの、「知りたいことはまずAIに聞いてみる」という行動が徐々に一般化しつつあります。
これはサイトオーナーにとって見逃せないトレンドです。
なぜなら、ユーザーがAI経由で情報を入手するようになると、自分のサイトやコンテンツがAIの回答に含まれるかどうかが、新たなアクセス流入の鍵となるからです。
この変化により、従来のSEO(検索エンジン最適化)だけでなく、AIからも選ばれるサイト作りが重要になりました。
具体的には、自社のコンテンツが大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の学習データや回答生成のソースとして参照されることを目指す必要があります。
そこで登場したのがLLMO(Large Language Model Optimization)対策、いわば「AIに評価されやすいサイト最適化」です。
LLMO対策の必要性
- 従来のSEO:
Googleに好まれる=検索上位に表示されるための最適化 - LLMO:
AIに好まれる=ChatGPTなどが回答生成時に引用するための最適化
今後のサイト運営では、以下2つの視点が重要になる。
- SEO:検索経由の流入対策
- LLMO:生成AI経由の流入対策
生成AI経由のアクセスが増えるにつれ、LLMO対策の重要性はますます高まっています。
実際、ChatGPTやBing ChatなどのAIが回答を生成するときに、参照した情報源をリンク付きで示すケースも出てきました。
将来的には、AIが提供する回答の中で「〇〇によると…」という形で信頼できるサイトの情報が引用・紹介され、そこからユーザーがサイトを訪れる流れが一般的になるかもしれません。
また、ユーザーがAIから得た情報で興味を持ち、詳しく調べるためにその情報元となるサイトを検索することも考えられます。
つまり、「検索エンジンから見つけてもらう」だけでなく、「AIに引用・参照してもらう」ことが新たな集客チャネルとなりつつあるのです。
これに対応するためには、私たちもサイトの作り方やコンテンツ戦略をアップデートする必要があります。
LLMO対策は決して従来のSEO対策を無視したり置き換えたりするものではありませんが、その延長線上に新たな最適化観点を加えるものと言えるでしょう。
SEOとLLMO、両方の視点を持つハイブリッド戦略こそが、これからのウェブ集客には求められています。
ねぎお社長の視点:本質的なLLMO対策
最近、「LLMO対策」と称してこんな話もよく見かけます。
- 記事構成を“PREP法”にするとAIが読み取りやすい
- ファクトを箇条書きでまとめておくとAIが拾いやすい
- 見出しに結論を書くのが効果的
確かに“通用する場面もある”かもしれませんが、本質的ではない「小手先のテクニック」に過ぎません。
確かにコンテンツをAIに読み取りやすく工夫することも大切ですが、私はそれ以上に本質的な戦略に目を向けるべきだと考えています。
これは従来から言われてきたSEOの真髄とも共通する部分です。
AI時代になっても結局重要なのは、「ユーザーとAIの両方にとって価値のある情報」を発信し、信頼される発信者になることではないでしょうか。
そこで、LLMO時代の本質的な対策として私が特に重視している3つのポイントをお伝えします。
1.自社ブランドを高める(信頼性・専門性の強化)
→ 信頼される発信者・企業になる
- 「この分野ならあの会社だよね」と思われる存在に
- 専門性・実績・信頼性を積み重ねることがAIにも伝わる
- 実名執筆や専門家監修も有効
情報があふれる中で、AIもユーザーも信頼できる発信源の情報を優先します。
自社のブランド力を高め、「この分野なら〇〇社の情報が信頼できる」と認識してもらうことが大切です。
具体的には、自社の専門分野で実績を積み上げたり、権威ある機関や専門家との提携・認証を得たりすることで、サイト全体の信頼性(Credibility)と専門性(Expertise)を底上げしましょう。
ブランド力が向上すれば、AIが回答を生成する際にも信頼性の高い情報源として選ばれやすくなります。
2.高品質なコンテンツを発信する(独自性と価値ある情報の提供)
→ 他にない独自性・深み・一次情報が鍵
- AIは“よくある情報”には興味を示さない
- 「誰が言っても同じ話」ではなく、「この会社だから言える話」を
- 体験・実績・統計・独自分析などを盛り込む
AIに評価されるためには、結局コンテンツの質が重要です。
他にはない独自の視点やデータ、深い分析に基づくコンテンツは、AIから見ても人から見ても価値があります。
ただキーワードを散りばめただけの記事や、他サイトの受け売り情報ではAIの学習済みデータに埋もれてしまい、
わざわざ引用する価値がないと判断されてしまいます。
そうならないためにも、「自社だから提供できる情報は何か?」を常に考え、オリジナルな切り口でユーザーの課題解決に役立つコンテンツを作成しましょう。
統計データや業界の最新トレンド、自社独自の調査結果など、一次情報や深掘りした記事はAIからも高く評価される傾向があります。
質の高いコンテンツを継続的に発信することで、AIの学習データに組み込まれやすくなり、結果としてAI経由の流入増加につながります。
3.様々なチャネルを活用して発信する(マルチチャネル戦略で影響力を拡大)
→ マルチチャネル展開で“AIに学習される機会”を増やす
- Webサイトだけじゃない → X(旧Twitter) / YouTube / Note / プレスリリース / メディア寄稿 etc.
- あらゆる場に自社情報が出ることで、AIの“知識”に組み込まれる
- 「何度も目にする=信頼できる」と判断されやすくなる
ウェブサイトの記事だけでなく、SNS投稿、動画、プレスリリース、ウェビナーなど多様なチャネルで情報発信することも、LLMO対策の一環です。
チャネルを広げることで、より多くのユーザーにリーチできるだけでなく、AIに触れられる機会も増えます。
例えば、専門的な内容を解説したYouTube動画や業界誌への寄稿記事など、形式を変えて情報発信することで、自社の知見がより広範に蓄積・共有されます。
これによりブランドの露出度が上がり、AIが学習するデータセット内に登場する確率も高まります。
また、SNSでのエンゲージメントが増えれば、人々の会話の中でブランド名やコンテンツが語られ、それもAIが学習するデータに含まれる可能性があります。
マルチチャネルに展開しつつ、一貫したメッセージと価値提供を行うことで、「どの媒体でも信頼できる発信者」としての評価を確立できるでしょう。
以上の3点は、一見すると当たり前のようですが、AI時代においてますます重要性を増す本質的な施策です。
小手先のテクニックだけで一時的にAIに取り上げられても、土台となるブランド力やコンテンツ力が伴わなければ長続きしません。
逆に、これらの基本をしっかり押さえておけば、新しいAI技術が出てきても揺るがない強みとなります。
まとめと今後の展望
本質的なLLMO対策 ≒ SEOの王道
- ブランドを高め
- 質の高いコンテンツを発信
- 多くのチャネルで露出を増やす
この地道な積み重ねが、AIにもユーザーにも選ばれるサイトとなる。
生成AIの普及によって生まれたLLMO対策は、実は従来のSEOと地続きの戦略とも言えます。
結局のところ、検索エンジンであれAIであれ、ユーザーにとって価値あるコンテンツや信頼できるサイトを評価する点に変わりはありません。
これからのウェブ戦略の中核には、「価値ある情報提供」と「ブランド力の構築」という不変のテーマが据えられるでしょう。
私たちサイト運営者は、SEOで培ってきた知見を活かしつつ、新たなAI時代のトレンドも取り入れて前進していく必要があります。
LLMO対策とSEO対策は対立するものではなく、互いに補完し合う関係です。
今後は検索結果上位表示だけでなく、AIの回答に自社情報がどう組み込まれるかまで視野に入れた総合的なコンテンツ戦略が求められます。
最後に強調したいのは、技術が変われど「人に役立つものを作る」という本質は変わらないということです。
AI時代でも、人々は価値ある情報や信頼できるブランドを求めています。
それを提供できるサイトであり続ける限り、きっとAIにもユーザーにも選ばれる存在になれるでしょう。
これからも変化の激しいデジタルマーケティングの世界ですが、基本を忘れず、しかし新しい波には柔軟に適応しながら、ともに成長していきましょう。
では、また!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■SEOコンサルティングのご相談は下記より、お気軽にご連絡をお待ちしております。
https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/seo-consulting#sec9
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー