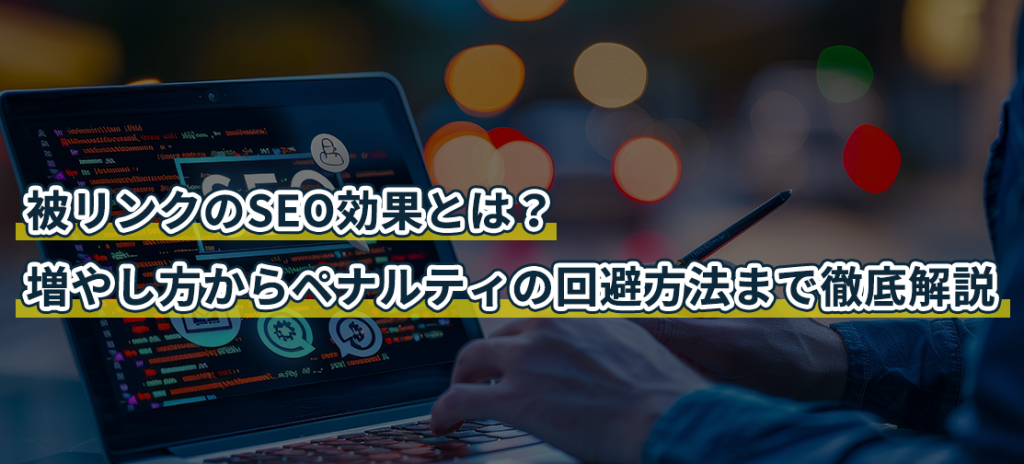ブログ
Google検索オフィスアワーまとめ(2025年4月24日)
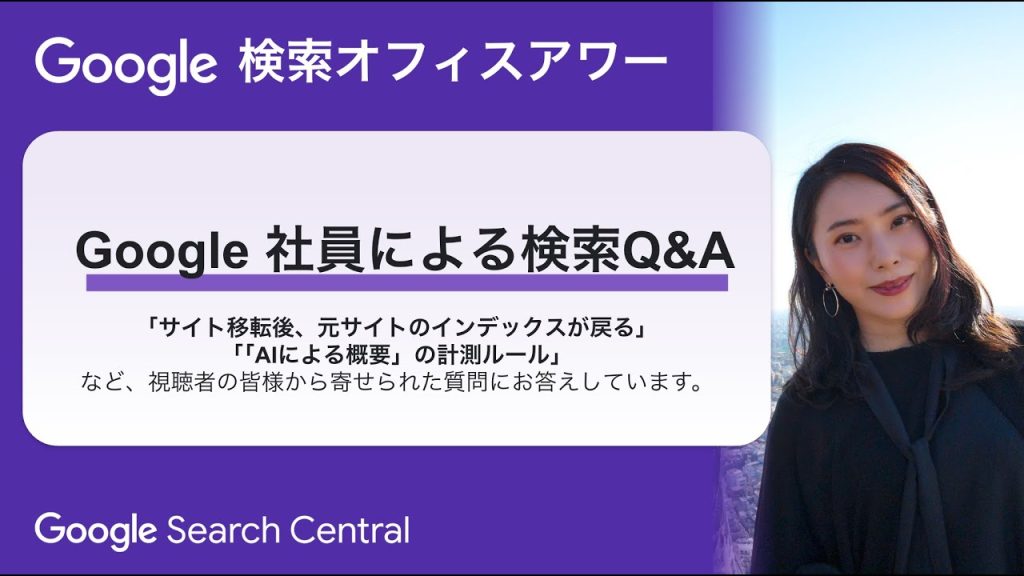
Google検索オフィスアワーまとめ(2025年3月27日)
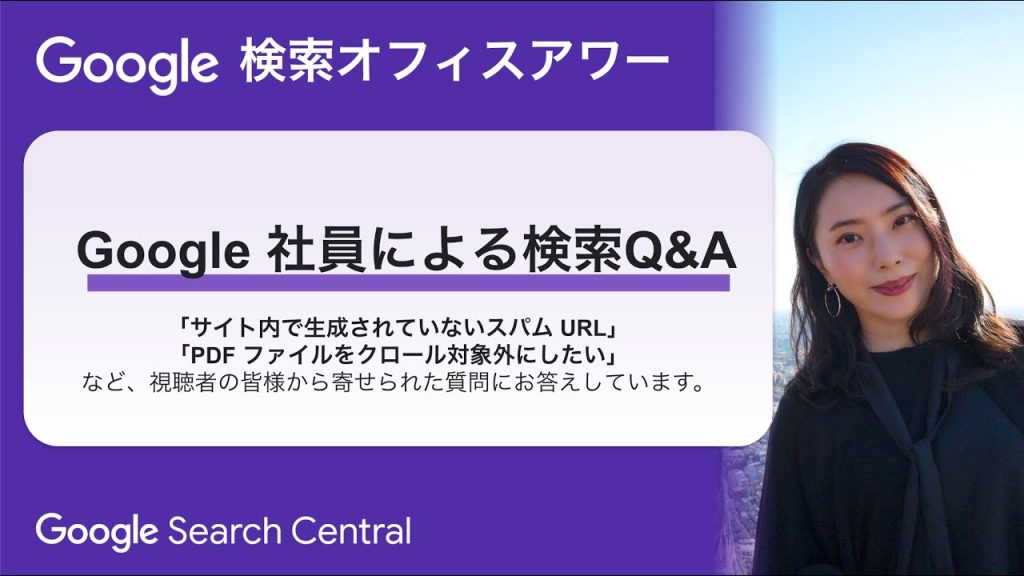
- #Google検索オフィスアワー
- #ウェブマスターオフィスアワー
Google検索オフィスアワーまとめ(2025年2月27日)
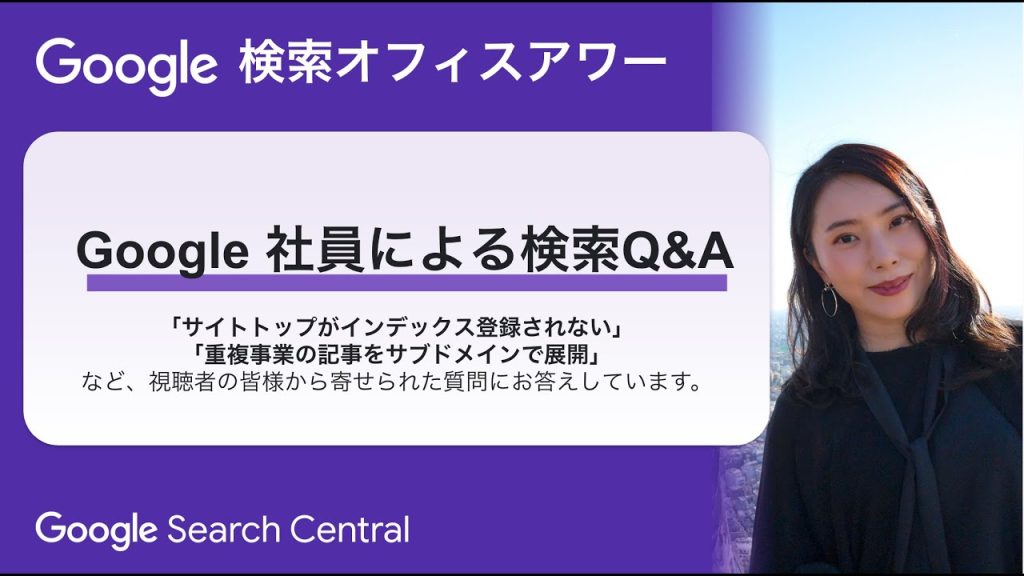
- #Google検索オフィスアワー
- #ウェブマスターオフィスアワー
Google検索オフィスアワーまとめ(2025年1月30日)
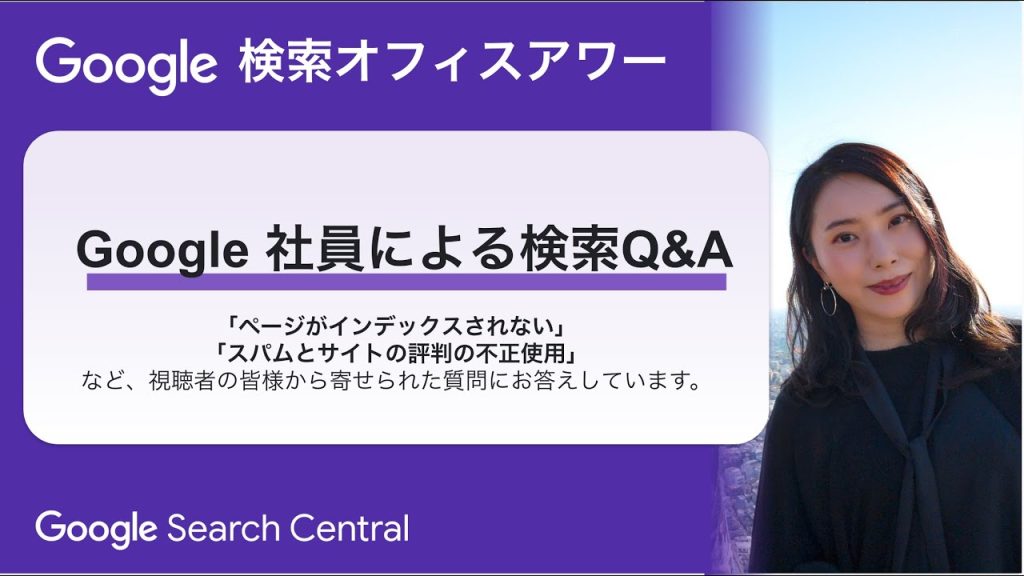
- #新年のご挨拶
2025年 新年のご挨拶

- #SEO評価
- #検索ランキング
SEO評価を高めるには?検索ランキングの重要要素と評価向上の実践方法
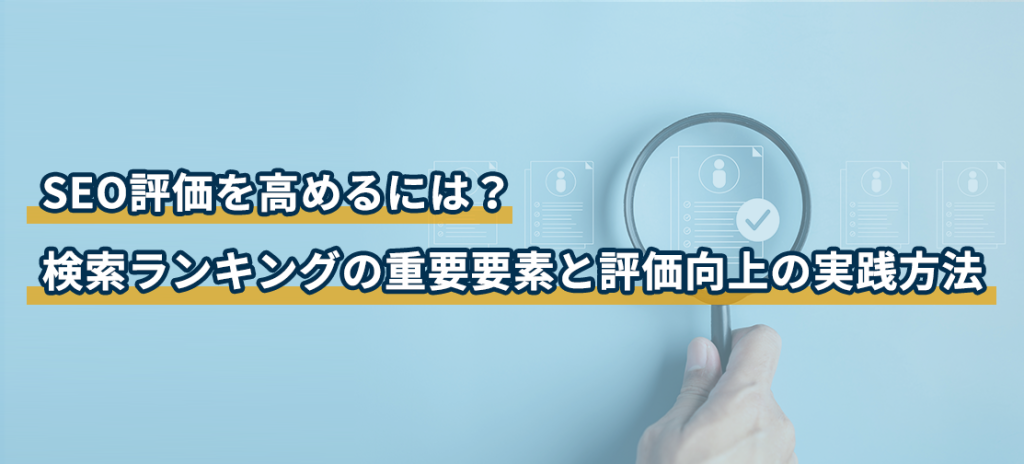
- #CTAボタン
効果的なCTAボタンの設計と最適化のガイド
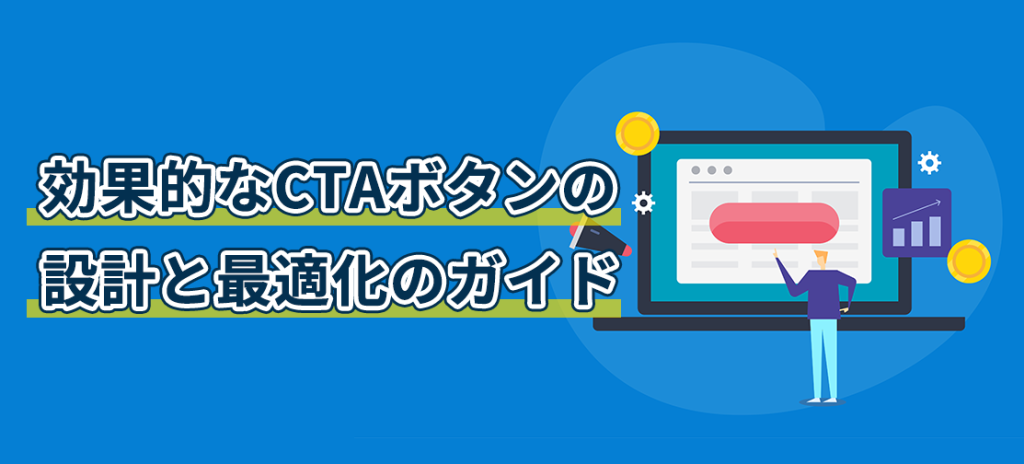
- #SEOツール
SEOツール「Ahrefs」の基本的な使い方とSEO最適化の方法
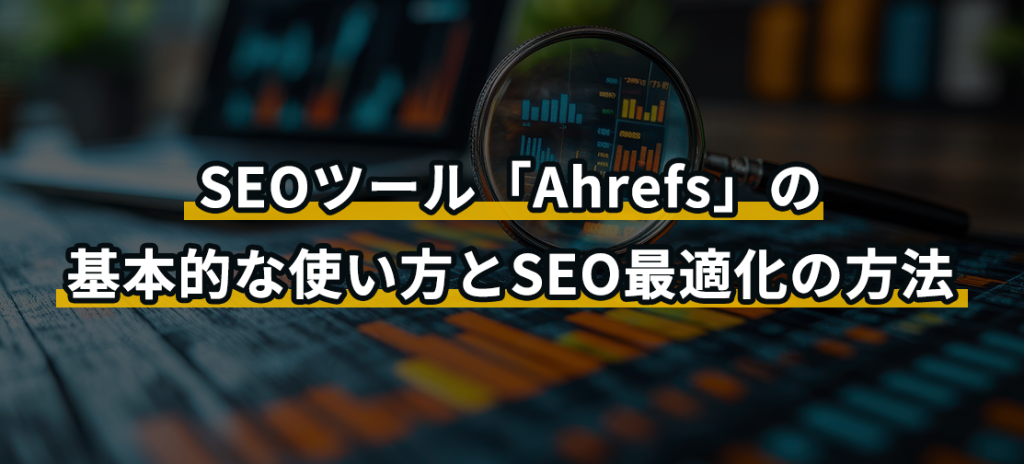
- #Google検索オフィスアワー
- #ウェブマスターオフィスアワー
Google検索オフィスアワーまとめ(2024年11月28日)
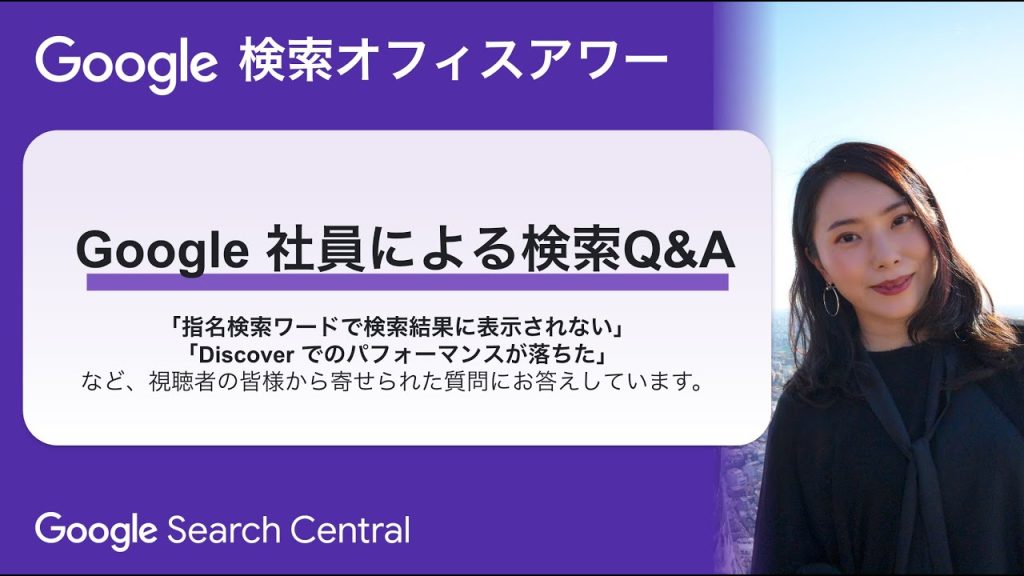
- #ペナルティ
- #被リンク
被リンクのSEO効果とは?増やし方からペナルティの回避方法まで徹底解説