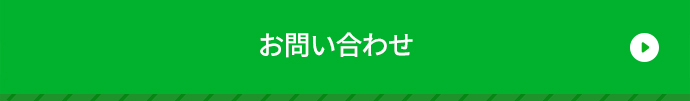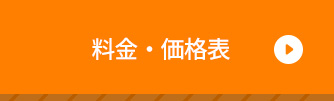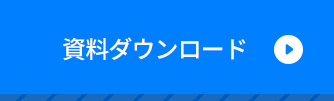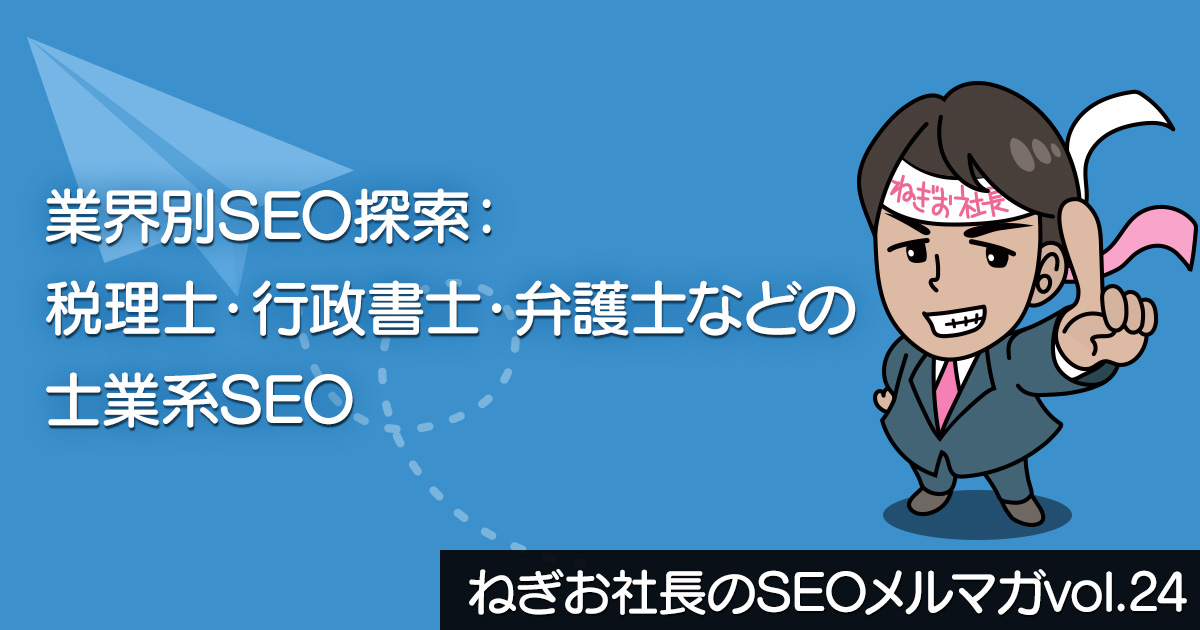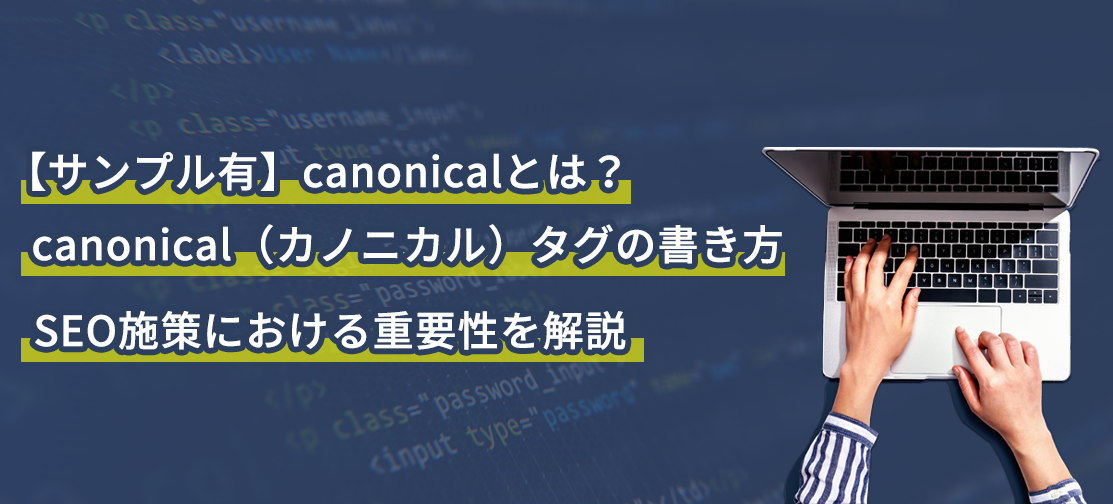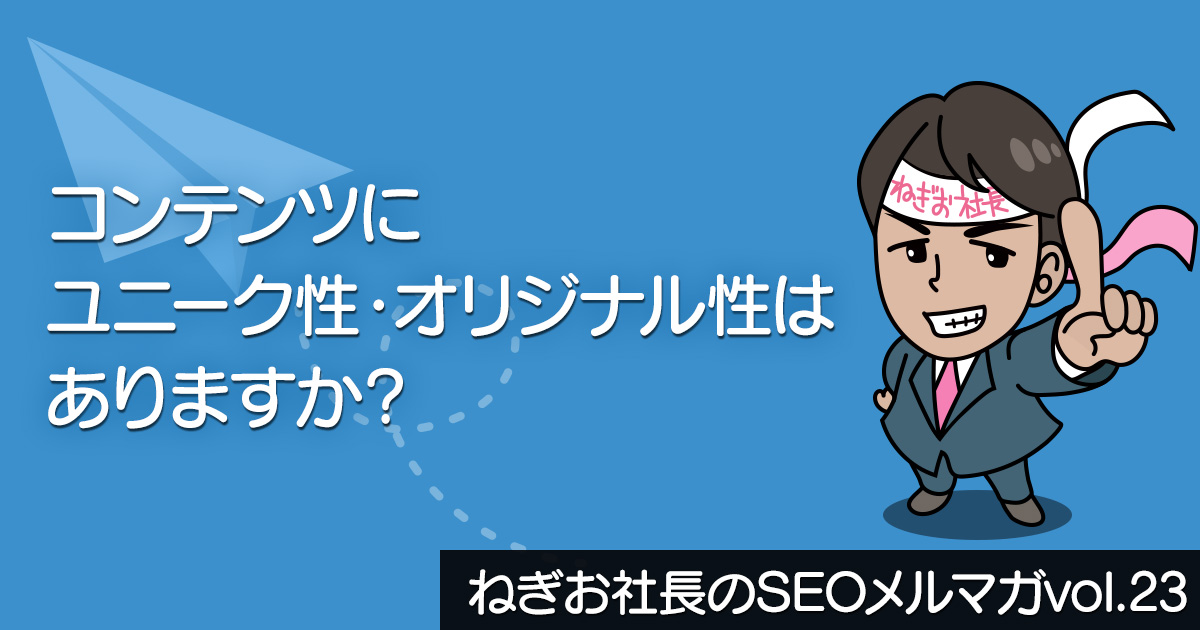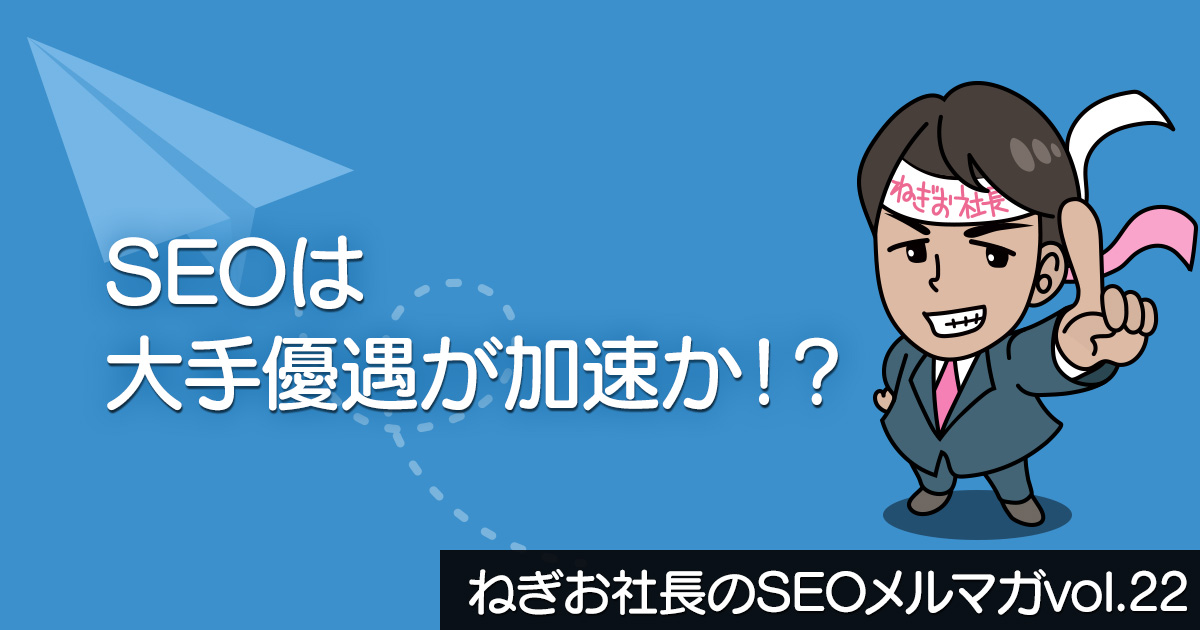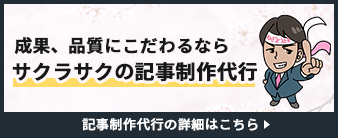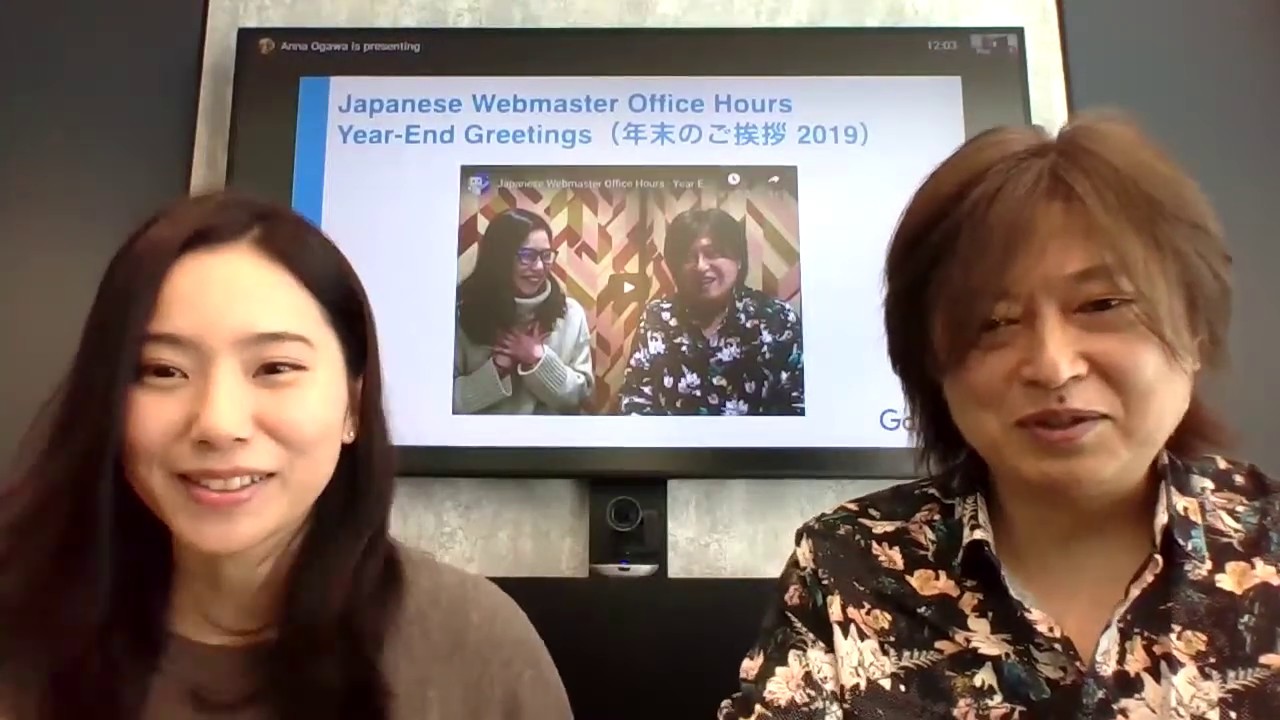
2020年1月30日に今年最初のウェブマスターオフィスアワーが行われました。
いつも通り、Googleの金谷さんとあんなさんがユーザーからの質問に回答しています。
この記事では回答の要点を中心にまとめています。
Q&A
サジェストを不正に操作する営業を受けた場合
Q. 同様のクエリで大量に検索してサジェストを荒らすことはガイドライン違反になるのか。
A. Googleが何をしているかを伝えることはできない。DMやサジェストのフォームから報告してほしい。
なお、サジェストは簡単に操作できるものではない。
人為的に操作したサイトは評判を落とすことにもつながる可能性がある。
data-nosnippet属性の影響範囲
Q. data-nosnippetについて以下の認識は正しいのか
A. 囲った箇所のコンテンツ評価は下がらないのか →その通りだが、クリックには影響する可能性
強調スニペットにも引用されないのか →その通り
各種リッチリザルトにも引用されないのか →リッチリザルトは構造化データで表示させようとしてマークアップするものである。基本的にはリッチリザルトを制御するものではない。
構造化マークアップなしの引用(日付引用や<table>など)もされないのか →確認中であるが、影響すると考えられる。
予期しないスニペットの表示
Q. MFI移行済みのPCと別URLのモバイルサイトを保有しており、PCの検索結果にモバイルサイト用のディスクリプションが表示される
A. 想定通りの挙動である
モバイルのクローラーが取得したデータが検索結果に反映される
PCとモバイルのデータをそろえることをおすすめ
PCとモバイルの別URLでの運用することは推奨していないので、動的に出しわけるかレスポンシブにすることを推奨
MFI移行後、意図しない検索結果表示になった
Q. PCと別URLのモバイルサイトを保有しており、MFI移行時からサイトリンクがPCで検索したときにもSP向けのURLになっている。URL検査での正規URLはPCのまま
A. 調査中であるが、もしかするとcssやJavascriptなどのファイル配信が遅れる、タイムアウトしてしまう可能性もある
セパレートURLは推奨しておらず、動的配信かレスポンシブをおすすめ
MFI最新ドキュメントのlazyloadの制限
Q. “Don’t lazy-load primary content upon user interaction.”の解釈
A. ページを開いた当初ユーザーが見えていないところをレンダリングしないlazy-loadについて、ユーザーのスクロールやクリックなどのアクションがあった際に初めて表示されるコンテンツは、Googlebotがアクションを行わないために読み込むことができない。
結果としてPCとSPとでコンテンツが異なることになってしまう。
重要なコンテンツはアクションを必要とせずに表示されるようにする。
※注
lazy-load以外にも、表示のためにアクションを必要とするコンテンツ全般に言えることであると考えられます。
Don't lazy-load primary content upon user interaction.https://t.co/YqzqAKRLjI
→Chromeの標準lazy-loadではなく、ユーザーのスクロールやクリック等を要するlazy-loadはGooglebotがアクセスできない場合があります。#ウェブマスターオフィスアワー
— 【SEO研究所】サクラサクラボ (@sakurasakulabo) January 30, 2020
rel=”canonical”で正規化が効いていない
Q. 自分ではパラメータを付けていないのにパラメータ付きのアドレスがインデックスされてしまう。
A. すでにリダイレクトが行われているため、いずれこの問題は解決すると思う。
考えられる原因としては、パラメータ付きのURLがインデックスされて、リンクもパラメータがついていたことが考えられる。カバレッジレポートなどで時期の特定もできる。
非SSLサイトからのリンク
Q. 非SSLサイトからリンクにあるのに表示されない。無効化(もしくは評価ダウン)された可能性はあるのか。
A. そんなことはない。
コンテンツの改善に専念してほしい。
コアアップデートでランキングが下がった
Q. 美容系ecサイトでサイト最適化しても順位が上がらない
A. 1月のコアアップデートで少し回復している模様。
基本的にはコンテンツが大事
ユーザーのためにコンテンツを作っていても順位が下がるのではないかという指摘については、どんどん競合が増えていて、いいコンテンツを作っても上位に入れない可能性がある。またGoogleが評価できていない可能性もある
それでもコンテンツが大事
また、検索だけにトラフィックを頼ることはおすすめしない
監修者のページは有料リンクになり得るのか
Q. 様々なウェブサイトで増えている「監修者」について、監修者のホームページからnofollowをつけずにリンクを設置している場合は有料リンクに該当するのか
A. リンク設置により順位を上げる意図があったかなどから総合的に判断する。
基本的には監修することや、監修したことを紹介するためにリンクすること自体も問題ない。通常このリンクにnofollowを使う必要ははないが、順位を上げる目的でやるべきではない
フィッシング詐欺サイトからのメールの報告方法
Q. フィッシング詐欺サイトからメールを受信した場合、Googleにはどのように報告するのが最良なのか。
A. 対Googleについてはフィッシングサイトの報告フォームから行ってほしい(処理に時間がかかるなどタイムラグがあることも)
https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=ja
Google以外にも報告するとよい
中古ドメインの報告先窓口はありますか?
Q. 順位上昇を目的として利用しているサイトを通報する窓口はありますか?
A. 専用の窓口はない。ガイドラインに違反しているのであればスパムレポートから送ってほしい。
なお、中古ドメインについては、中古ドメインさえ使えば有利にならないように特別視している。
中古ドメインだけが理由で上がらないようにしている中で、目についた中古ドメインがセンセーショナルで嫌悪の対象になっているのではないか
Googleはそういったことが例外的にでも発生しないよう取り組んでいる
中古ドメインについた被リンク
Q. 中古ドメインを購入して運営しており、現在運営しているサイトとは関連のないリンクがあるが否認すべきなのか
質の低いリンクは無効化されるので放置でもいいのか
A. 否認ツールは特に使わなくてよい。
質の低いリンクによって手動対策がなされているのならば再審査リクエストが必要。自分が設置したものであれば否認が必要。
質の低いリンクはランキング要素には考慮していないが、スパム認定にはかなり考慮している。
現在のサイトと関係ないリンクや現在のコンテンツと関係ないキーワードで来ている人がどれくらいいるかを見て、それほどいないのであれば気にしなくてよい。
YMYL領域の背景、解釈
Q. YMYLという概念はなく、お金が動くワードを飛ばして広告を出させようとしているというのは本当なのか
A. そんなことはない
広告のためというのであればYMYL以外にも広告市場が大きい(低単価高需要など)ものもあるのでYMYLだけを落とすこともしていない。(もしそういう意図があるのであれば全ジャンルを落とせばよく、YMYLを狙い撃つ意味がない)
また、下がったサイトもあれば上がったサイトもあるが、広告費を出したサイトを優遇したわけではないし、広告費を出しそうなサイトを下げたわけでもない(上がれば広告費を出さなくなる場合もあるし、非効率)
また、検索と広告は分けて考えており、検索で広告が最大になるようにはしているが、広告費を払っているからと言って個別に検索についての優遇はしない(順位・情報など)
その他直近のニュース
年末公開の動画
- 技術的な関心を持っている人が増えてきた
- コンテンツ作成者が増えた(競合が増えた)
イベント
1/28 コンテンツマーケティングジャパン東京
ブログ
初心者向けの動画シリーズ
https://webmaster-ja.googleblog.com/2020/01/video-series-for-new-webmasters-search.html
- コアアルゴリズムアップデート
- デスクトップUIの変更 → その後再テストのアナウンス
- data-vocabularyサポート対象終了
- 強調スニペットの表示変更
次回のウェブマスターオフィスアワーは二月後半(日時未定)とのことです。